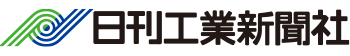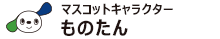セミナー
【ライブ配信セミナー】
「設計コストダウンのプロ」が「体系的」に解説!
若手向け「設計コストダウン7手法」
~ベテラン設計者がもつ、設計コストダウンの手法・切り口を設計コストダウンのプロが解説~
開催主旨
世界的なインフレ・部材高騰が止まりません。
貴社でももっと「コストを落とせ!」という声が溢れているのではないでしょうか。
しかし、コストを落とせといわれても…
「コストオーバーで上から詰められる。設計でどうやって下げる?」
「営業が安くしろって言うけど、品質落とせない…」
「材料費高騰でコストダウン無理ゲー」
「購買の部材ミスで設計変更、工数倍増」
「部品点数多すぎて組立工数爆増。どうやって減らす?」
「コスト下げたら不良品増えたわ。どうやってバランス取りゃいいの?」
などなど…。
「正直どうしたらいいの?」と悩んでいる若手設計者の方は多いと思います。
昔は、設計段階でのコスト削減・工数削減のポイントを教えてくれるベテラン設計者が居り、若手にコストダウンの考え方を教えてくれたものですが、ベテランがもう居ない、または多忙すぎるという難しい現場も増えています。
こうしたことから、ベテラン設計者が持つ、コストダウンの視点・切り口。加工工数、組込工数を削減、部品点数削減、一体化、軽量化、材料最適化…などを「体系的」に一日で学習するプログラムを企画いたしました。
「中量生産・少量生産・リピート生産」現場に於いてはこれらの手法を設計基準にすることで生産最適化・コストダウンをスムーズに実現できます。
コストダウン圧力に悩む方、周りに教えてくれるベテラン設計が居ないという方、営業や購買に振り回されて困っている方、ぜひご活用ください。
本セミナーのテキストは、PDFにてお送り致します。
※お申込みの際に、テキストを受け取れるメールアドレスを記入して下さい。
(申込アドレスと異なる場合は、申し込みフォームの備考欄にてお知らせ下さい。)
概要
| 日時 | 2026年2月25日(水) 10:00~17:00 (9:30 ログイン開始)※昼休憩1時間あり |
|---|---|
| 会場 | WEBセミナー |
| 受講料 | お一人様:46,200円(資料含む、消費税込)
受講にあたり |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 申込締切日について | 2026年2月24日(火)17:00〆切 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 事業推進部(セミナー係) TEL: 03-5644-7222 FAX: 03-5644-7215 E-mail : j-seminar@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
| FAX申込について |
講師
プログラム
| 手法1. 「無駄を省く」に注力したコストダウン法 |
|
a.試作品製作時は機能チェックで量産生産移行時はコストダウンをおこなえる設計に改善すべき内容 b.部品点数削減効果を試作製作時から量産製作へ移行するときにおこなうべき事 c.材料最適化がもたらす効果を類似品でも違う図面から同等形状にできる部分を増やして加工工数削減、少量生産でも量産効果を発揮出来る手法 d.同形状ユニットのリピート設計時、極力同形状部分を設定して長さ、幅等のみを変更して加工しやすさを追求した設計でコストダウンをおこなう |
|
手法2. 加工設備を考えたコストダウン法 |
| a.工場設備を考え、設計した図面より「手離れの良い形状」を考えて「加工工数削減」、安定した品質に出来る設計 |
|
手法3. 「手離れの良さ」を追求したコストダウン法 |
|
a.一体化加工で見た目は加工性が良く見えても加工工数の削減が出来ない、分割化による重切削加工で加工工数の削減を計る |
| 手法4. 「手作業を省略」を追求したコストダウン法 |
|
a→ネジの数は組み込み工数に比例で少量生産でもリピート生産ではネジ以外の組込方法採択で手作業を省いてコストダウンをおこなう b→異形状部品のユニットは精密治具を必要とし治具代でコストアップになる為、部品自体の簡略化を図りコストダウンをおこなう |
| 手法5. 「中量・少量生産」に適したコストダウン法 |
|
a→類似形状品の生産には仕掛かり形状までの製作で少量生産でも大量生産に見合う製作が出来る事で加工工数削減を計りコストダウンをおこなう b→1台ずつ完成品にするユニット製作から仕掛かり状態で在庫にして注文が入った時点で完成品にする生産方法のメリット(コスト、納期、在庫スペース等) |
| 手法6. 試作から量産製作へ移行するときに考えるコストダウン |
| a→試作時に機能チェックを重視して量産生産時には加工工数削減を行える形状で機能が同様になる形状の設計をおこなう
b→試作時に仕様が増えて部品点数もそれに合わせて増えた形状を量産時には一体化を考えた設計で部品点数を増やさなくて済む形状設計をおこなう |
|
手法7. 不安定な形状はコストアップで「同形状でも安定した形状」を考えたコストダウン |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |