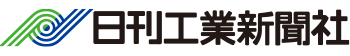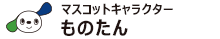セミナー
企業競争力・顧客満足力強化で、生き残りを目指す!
生産計画・工程管理力強化セミナー
新たな生産管理による“企業競争力”と“顧客満足力”の強化
開催主旨
コロナ禍の収束後も生産現場のコミュニケーション大幅低下の影響が残り、生産現場で働く人の多様化も進んでいるため、品質不良や生産現場のトラブルが多発し、生産計画が未達となり、納期遅れなど顧客満足度の低下を生じています。
このような状況下においては、「生産管理と工程管理の“新たな”仕組みづくり」に取り組まなければ、モノづくり企業として生き残れなくなっています。
本セミナーでは、生産管理の仕組みを再構築し、さらに生産計画・改善に展開してゆく方法を、執筆本「生産管理ハンドブック」を使ってわかりやすく解説するとともに、すぐに使える講師の指導実績ある多くのフォーマットもご提供いたします。
(注)本セミナーは、「デジタル化」ではなく、「新たな仕組みづくり、人づくり、組織づくり」をテーマとしています。
受講対象者
・製造部門の管理者・監督者、生産管理部門の管理者・監督者、改善担当者など
(注)コンサルタント業の方の参加申込みは、ご遠慮下さい。
受講特典
本セミナーを受講される方には、講師の著書「生産管理ハンドブック」を当日進呈いたします。
概要
| 日時 | 2025年 7月 8日(火) 10:00~17:00 (9:30 受付開始 休憩60分) ※昼食のご用意がございませんので、ご準備いただくか休憩時間内に外食いただきますようお願い申し上げます。(休憩時間の会場内飲食は可能) |
|---|---|
| 会場 | 日刊工業新聞社名古屋支社 6階セミナー会場 ※会場には受講者用の駐車場が有りません。必ず最寄りの公共交通機関でご来場ください。 ※当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 |
| 受講料 | 48,400円(資料含む、消費税込) ※日本金型工業会、中部プラスチックス連合会の正会員の方は15%割引とさせていただきます。 |
| 主催 | 日刊工業新聞社
※弊社プライバシーポリシー(個人情報保護方針)をご一読いただき、申込みフォームより必要事項をご入力ください。 |
| 申込について | 受講にあたり 開催決定後、受講票並び請求書をメール(PDFファイル)にてお送り致します。 申込者が最少催行人数に達していない講座の場合、開催を見送りとさせて頂くことがございます。(担当者より一週間前を目途にご連絡致します。) 申し込み方法 各セミナーのお申込みフォームからお申込みいただくか、FAX申込書をダウンロードしご記入のうえ、FAXにてお申込みください。 受講料 振込手数料は貴社でご負担願います。 キャンセルについて 開催日1週間前までの受付とさせて頂きます。1週間前までにご連絡がない場合はご欠席の方もキャンセル料として受講料全額を頂きます。 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 イベント事業部・事業推進部(名古屋) TEL:052-931-6158 FAX:052-931-6159 E-mail:nk-event@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
| FAX申込について |
講師
会場アクセス
-
日刊工業新聞社名古屋支社
6階セミナー会場
名古屋市東区泉2-21-28 - セミナー会場案内図
プログラム
|
Ⅰ.[生産と生産管理の基本] |
| (1)生産現場の急激な変化と生産管理の新たな展開 (2)モノづくりに必要な要素とは (3)モノづくりの生産の流れを円滑にするには (4)モノづくりを確実にする仕組みとは (5)生産現場の基本要素は6Mだ |
| 2.市場の変動に対応する生産方式の変化 |
| (1)生産方式はどのように変化しているのか |
| 3.企業の生き残りがかかる生産管理とは |
| (1)生産管理がなぜ必要なのか (2)生産管理の基本サイクルとは何か (3)生産管理の個別業務の流れとは何か (4)生産管理を支える他部門の管理手法とは何か |
| Ⅱ.[生産計画の基本] 1.市場ニーズに応えるための生産計画とは |
| (1)生産計画とはどのようなものか (2)長期の大日程計画と中日程計画の違いは (3)短期の小日程計画で何ができるか |
| 2.顧客満足を実現する中日程計画の立て方とは |
| (1)中日程計画とはどのようなものか (2)手順計画で工程と作業を計画する (3)工数計画で生産能力を「見える化」する (4)負荷計画で能力と負荷のバランスをとる (5)日程計画で納期を確保する |
| 3.生産計画の精度を高めるための手法とは |
| (1)現在の生産現場に求められる作業標準書とは (2)作業標準書をうまくつくるポイント (3)標準時間を生産計画に活用するポイント (4)標準時間を設定する方法 (5)QC工程表をうまくつくるポイントとは |
| Ⅲ.[工程管理の基本] 1.付加価値を創造する工程管理の進め方とは |
| (1)工程管理とは何をすることか (2)工程管理を確実にする作業手配とは (3)進捗管理によって工程遅れを挽回する (4)余力管理によって手持ちを防止する (5)現品管理によって仕掛在庫を防止する (6)事後管理によって生産実績を把握し改善要求する |
| 2.工程管理をうまくやる秘策を知る |
| (1)工程管理をうまくやる秘策には何があるのか (2)まず「本物の5S」で見える・分かる・できる生産現場をつくる (3)「見える化」で問題を先取りし快善力を強化する (4)作業標準書の定着で変化に強い生産ラインをつくる (5)作業者の育成によって生産計画達成の基盤をつくる (6)監督者の日常基本行動によって工程管理を実践する (7)「3礼」によって工程管理サイクルを確実に廻す (8)監督者の生産現場パトロールで先取り管理をする (9)報・連・相で作業者の責任を明確にする (10)多能化に取り組んで人の変化に強い生産現場をつくる |
| 3.問題解決力強化で生産目標を達成せよ |
| (1)新たな生産現場問題の背景に何があるか (2)問題の本質をとらえる眼を持つ |
| Ⅳ.[現場改革の基本] 1.競争力を強化する現場改革とは |
| (1)生産現場の体質を改革するステップとは (2)リードタイム短縮を実現するには |