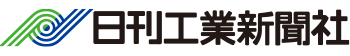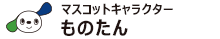セミナー
【ライブ配信&後日の録画視聴可】
ゾンビ事業からの脱却!経営者、
企画担当者、現場を率いる営業・技術部門の責任者向け
顧客の課題を先取りし、
高ROEを実現する戦略的ソリューション事業構築
~高収益事業へ進化する3つの行動変革ツール~
開催主旨
「売っても儲からない」といった“ゾンビ商品・事業”に終止符を打ちませんか?顧客の要望に受け身で対応し、時間ばかりが奪われるゾンビ事業から抜け出し、高収益なソリューション事業へと転換する具体的な方法があります。
本講座では、メーカー経営者や企画担当者、そして現場の営業・技術者の皆様が直面する「利益が出ない商品・事業」「営業・技術者の消耗」といった課題に対し、事業に関わる営業と技術者の「行動変容」という明確な解決策を提示します。具体的には、以下の3つの実践的な「ツール(道具)」を用いて、営業と技術が連携し、顧客の潜在的な課題を解決することで高収益テーマを創出する道筋を示します。
■潜在ニーズの仮説構築: 顧客自身も気づいていない本質的な課題を見つけ出すための方法
■顧客訪問時の検証: 商談やヒアリングの質を飛躍的に高め、信頼関係を築きながら課題を深く掘り下げる実践的なアプローチ
■課題解決型カタログ(ソリューションカタログ)の活用: 自社の技術を単なる商品としてではなく、ソリューションとして提示することで、新たな高収益事業を生み出す具体的な手法
これらの「ツール」を使いこなすことで、営業と技術が密に連携し、顧客の真の課題解決に貢献できる高収益型のビジネスモデルを構築できます。こうした事業に携わる人々の「行動変容」を促すことで、貴社の事業を「稼げる」体質へと変革し、高ROE(自己資本利益率)を実現することを目指します。単なる商品提供から一歩進んだ、未来志向の事業変革を目指す方に最適です。
受講対象
■メーカーの経営者の方・事業部長の方・事業部経営企画部の方
■営業系の部門長・担当役員の方
■技術系の部門長・担当役員の方
■新規事業担当者
■サービス実装を前提とした研究開発の担当者
【受講者特典】
参加者に、自社の研究開発の状況を診断するための問診票と修正のためのガイドラインを差し上げます。また、課題を明確化するオンライン会議の実施などの特典もあります。
本セミナーは、オンライン配信ツールZoomを使い、出演者自身も自宅から出演いただく形式の「Home to Home」(H2H)セミナーとなります。ご視聴方法(参加用URL等)はご登録くださいましたメールにお知らせいたします。
概要
| 日時 | 2025年 9月 2日(火)14:00~17:00 ※開催当日13:00まで受付 |
|---|---|
| 受講料 | 33,000円(テキスト代、税込、参加特典込み、録画視聴、1名分) ※開催決定後、受講にかかります受講料の請求書(PDF)をメールでお知らせします。 ※振込手数料は貴社でご負担願います。 ※当日の参加が難しい方は録画での参加も可能です。録画での参加を希望される方は、申込フォームの備考欄にその旨をご記載ください。 |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 問い合わせ先 | 日刊工業新聞社 西日本支社 総合事業本部 セミナー係 TEL : 06-6946-3382 FAX : 06-6946-3389 E-mail : seminar-osaka@media.nikkan.co.jp |
講師
プログラム
| 1.ゾンビ事業からの脱却 「売れない」「儲からない」事業に終止符を打つ |
| 1-1 営業と商品企画が陥る「ゾンビ化」のメカニズム 1-2 根本原因である「潜在ニーズへの無知」とはなにか 1-3 潜在ニーズ(行動)はソリューションに対する無知から生まれる |
| 2.成功事例に学ぶ、上流工程への食い込み方 |
| 2-1 共同開発で成功した企業のリアルな事例 2-1-1 3Mの事例・ヤマハ発動機の事例・ヤマハ発動機の事例2 2-1-2 東京エレクトロンのプロダクトマーケティングによるShift Left事例 2-1-3 SMCの事例 2-1-4 日東電工の事例 2-1-5 TDKの事例・村田製作所の事例・各企業の取り組みと考察 |
| 3.高収益を生む営業・商品開発の全体像 |
| 3-1 高収益を生み出すための「技術戦略」の重要性 3-2 R&Dテーマのパイプライン・マネジメントの観点から 3-3 研究開発テーマの管理方法や評価の方向性 3-4 技術プラットフォームの著名例 3-5 ソリューションカタログによるテーマの創出 3-6 ソリューションカタログによるデジタルマーケ活動のフロー 3-7 用途や解決出来る課題の探索 3-8 本講座で提案する既存顧客との共同研究に至る流れ 3-9 本講座で提案する新規顧客との共同研究に至る流れ |
| 4.顧客に「頼られる存在」になるための変革 |
| 4-1 医者理論・顧客の要望を聞けると思って商談に行っていないか? 4-2 医者は医者でもタダの医者は頼られない、なぜか? 4-3 あなたが八百屋の立場なら何を売るか? 4-4 商品スペックをアピールした資料を配っていないか? 4-5 頼られる人になるために必要なこととは? 4-6 商談前準備とは何か?なぜ必要なのか? 4-7 商談前準備の心構えと具体的な準備方法 4-8 商談の質を劇的に高める「商談前準備シート」 4-9 顧客の研究開発課題を調査するには? 4-10 顧客の生産上の課題を調査するには? 4-11 顧客の評価上の課題を調査するには? 4-12 背景となる技術・社会トレンドを把握するには? 4-13 商談前準備の事例 4-14 リード情報で顧客と会話する 4-15 頼られる・呼ばれるための実施事項 4-16 顧客が欲しがる情報をまとめる、提供する 4-17 顧客分析のフレームワーク、やり方 4-18 現行商談の顧客分析のフレームワーク、やり方 4-19 営業に求められる役割とは?開発に求められる役割とは? |
| 5.自社の技術や過去の成功事例を「ソリューション」として表現し直す方法 |
| 5-1 既存技術を「ソリューション」として見せる「ソリューションカタログ」の作成 5-2 ソリューション履歴の棚卸(フォーマット) 5-3 既存技術のソリューション的表現、事例 5-3-1 取り扱う事例(スピードガン) 5-3-2 このセミナーで取り扱う事例(不織布) 5-4 技術プラットフォーム・SLカタログによる課題解決ビジネス 5-5 生成AIで自社技術を棚卸し、新たな価値を創造する 5-6 さまざまなソリューションのカタログがマーケティング活動につながる 5-6-1 ソリューションカタログや中間品のイメージ 5-6-2 SLカタログ発達の3段階 |
| 6.顧客との「技術交流会」で共同開発へ |
|
6-1 共同開発を成功に導くための提案術 |
| 7.新しい市場・用途の探索とテーマ企画 |
|
7-1 特許やAIを活用した用途探索 |
| 8.新規顧客へのアプローチ |
| 8-1 デジタルで顧客と繋がる 8-1-1 SLカタログのデジタルマーケティングでの活用 8-1-2 デジタルマーケティング・オンラインセミナー・技術相談会の提案へ |
| 9.まとめ・講師からの特典(研究開発ガイドラインの提供、後日のオンラインによる課題明確化会議の実施など) |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |