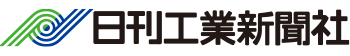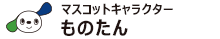セミナー
ライブ配信&後日の録画視聴も可能!
社会・顧客の変化を先取りして
未来を読む!自ら未来を創る!
R&Dのための「未来洞察」入門
~自社のビジョンと社会変化を結び付け、新たなテーマ創出を行う手法~
開催主旨
VUCAの時代と言われて久しいですが、第二次トランプ政権の発足により未来の見通しがより一層困難となっています。過去の経験則や現在の延長線上で物事を捉えるのみでは、企業や組織、個人は変化の波に乗り遅れるリスクに直面するのは必至であり、この不確実性の高い時代を生き抜くための“羅針盤”として、「未来洞察」が注目されています。
未来洞察は単なる未来予測ではありません。多様な情報源から未来の兆候を読み解き、複数のあり得る未来のシナリオを検討することで「ありたい未来」を自ら描き、その実現に向け、いま何を為すべきかを逆算的に考えるための体系的なアプローチです。
本セミナーでは、未来洞察の力を活用し、社会や顧客の変化を先取りした「機会領域」を創出することを目指します。
具体的には、マクロトレンドとミクロ事象の情報を掛け合わせることで未来社会のシナリオを構築し、そこから導かれる「自社の機会領域」を設定するプロセスを学びます。未来シナリオの構築、バックキャスト思考による機会領域の特定、企業ビジョンと社会変化を結合し、新たなテーマ創出へとつなげる手法を掴んでいただきます。ワークショップでは、Z世代を対象に価値観・行動様式をインタビューする機会(オンライン)を設けており、彼らを起点に行動様式から違和感、未来の兆しを得るコツが得られます。
本セミナーを通じて未来の不確実性に対応し、持続的な成長を実現するための羅針盤となる「未来洞察」のスキルを獲得しましょう。
概要
| 日時 | 2025年12月19日(金) 15:00~17:00(2時間講座) (14:30 受付開始) |
|---|---|
| 会場 | WEBセミナー WEBセミナーは、WEBミーティングツール「Zoom」を使用して開催いたします。 ※受講者による録音・録画は固くおことわり申し上げます。 ブラウザとインターネット接続環境があれば、どこからでも参加可能です。 |
| 受講料 | 11,000円(資料含む、消費税込、1名分) ※録画視聴は、当日参加された方も、録画視聴で参加登録された方も可能です。 ※録画視聴は、講座終了後10日間(12/31まで)にわたり何度でもご確認いただけます。 |
| 主催 | 日刊工業新聞社
※弊社プライバシーポリシー(個人情報保護方針)をご一読いただき、申込みフォームより必要事項をご入力ください。 |
| 申込について | 受講にあたり 開催決定後、請求書をメール(PDFファイル)にてお送り致します。 申込者が最少催行人数に達していない講座の場合、開催を見送りとさせて頂くことがございます。(担当者より一週間前を目途にご連絡致します。) 申し込み方法 各セミナーのお申込みフォームからお申込みください。 受講料 振込手数料は貴社でご負担願います。 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 西日本支社 総合事業本部 TEL : 06-6946-3382 E-mail : seminar-osaka@media.nikkan.co.jp |
講師
プログラム
| 1.未来洞察とは |
|
1-1 未来洞察とは |
| 2.ワークショップ |
| 2-1 ワーク1:マクロトレンドの考察 ①バックキャストからのアプローチ:発見的かつ一般性のある未来の社会像と機会領域を描く ②マイクロトレンドカードの活用 ③マイクロトレンドの創造的考察 2-2 ワーク2:ミクロ事象の考察 ①バックキャストからのアプローチ:ミクロな視点の利用 ②Z世代の価値観・行動様式のインタビュー ③ミクロな視点:未来社会の先行者と兆しの探索 ④エクストリームユーザーインタビュー(Z世代を対象に価値観・行動様式をインタビューします) ⑤タイムマップのインタビュー ⑥インタビューのポイントと方法 ⑦N=1を起点に行動様式から違和感、未来の兆しを得る 2-3 ワーク3:機会領域の探索 ①未来の社会シーンの発散的創出 ②機会領域シートの整理 ③テーマと機会領域、アイデアの関係性 2-4 全体発表 ①発表とリフレクション ②チェックアウト |
| 3.質疑応答・まとめ |