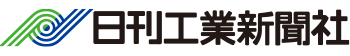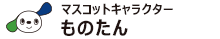セミナー
トヨタが実践する!全部署・全員参加型
「原価マネジメント」入門
~業務の中で原価を創造して先手で原価をつくり、原価低減を達成する手法~
開催主旨
経理・会計は「仕事の結果」を集計する業務です。仕事が終わった集計(会計)を眺めても業績向上にはつながらないのは当然で、儲けるためには日々の開発業務の中で付加価値をつくり(上げる)、原価を下げることが求められます。このように“現在の業務と付加価値を対にする”ことが原価マネジメントです。
トヨタでは、商品企画の時点であらかじめ原価を検討して見積もる「原価企画」を確立しており、開発以降の業務の規範とする(原価計画を立てる)ことで業務の中で原価を創造し、先手で原価をつくり上げています。そして、全部署および全員が原価を真から理解し、日々の開発・生産業務で、これらを実践することで原価低減を達成しています。
本講座では、生産結果を集計する従来型の原価ではなく、原価を理解し、創造し、先手でつくり上げる手法を解説。トヨタが実践する、商品企画と同時に原価の検討を開始し、目標とする原価を確実に達成したうえで設計・開発を進める効果を実感いただきます。同時に、業務と原価(または利益)がリアルタイムに直結する経営と管理の実践により、強い組織づくりにつなげていただきます。
※本セミナーでは会場での資料の配付は予定しておりませんので、講義資料をノートPCなどのデバイスに保存のうえ参加されるか、各自でプリントアウトされたうえでご参加くださいませ。
概要
| 日時 | 2025年 10月 21日(火) 10:00~17:00 (9:30 受付開始 休憩60分) ※昼食のご用意がございませんので、ご準備いただくか休憩時間内に外食いただきますようお願い申し上げます。(休憩時間の会場内飲食は可能) |
|---|---|
| 会場 | 日刊工業新聞社名古屋支社 6階セミナー会場 ※会場には受講者用の駐車場が有りません。必ず最寄りの公共交通機関でご来場ください。 ※当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 |
| 受講料 | 46,200円(資料含む、消費税込) |
| 主催 | 日刊工業新聞社
※弊社プライバシーポリシー(個人情報保護方針)をご一読いただき、申込みフォームより必要事項をご入力ください。 |
| 申込について | 受講にあたり 開催決定後、受講票並び請求書をメール(PDFファイル)にてお送り致します。 申込者が最少催行人数に達していない講座の場合、開催を見送りとさせて頂くことがございます。(担当者より一週間前を目途にご連絡致します。) 申し込み方法 各セミナーのお申込みフォームからお申込みいただくか、FAX申込書をダウンロードしご記入のうえ、FAXにてお申込みください。 受講料 振込手数料は貴社でご負担願います。 キャンセルについて 開催日1週間前までの受付とさせて頂きます。1週間前までにご連絡がない場合はご欠席の方もキャンセル料として受講料全額を頂きます。 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 イベント事業部・事業推進部(名古屋) TEL:052-931-6158 FAX:052-931-6159 E-mail:nk-event@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
| FAX申込について |
講師
会場アクセス
-
日刊工業新聞社名古屋支社
6階セミナー会場
名古屋市東区泉2-21-28 - セミナー会場案内図
プログラム
| 1.原価管理の概要 |
| 1-1 原価マネジメントの必要性 1-2 業務と原価の関連 1-3 経理部の役割 1-4 原価マネジメントの仕組み 1-5 原価マネジメントの資格者 |
| 2.原価計算の基礎(演習問題あり) |
| 2-1 原価の多面性 2-2 生産量変動よる原価計算(変動費・固定費分類) 2-3 差額原価と絶対原価 2-4 意思決定法(経済性検討) 2-5 実績原価・標準原価・予想原価 |
| 3.商品企画・製品企画 |
| 3-1 トヨタのCE制度 3-2 商品企画・製品企画と原価企画 3-3 経理部の役割 3-4 原価マネジメントの仕組み 3-5 原価Mの資格者 |
| 4.原価による意思決定(経営) |
| 4-1 代表的な原価面からの意思決定法 ― 例題から学ぶ経済性検討 4-2 各種の業務と原価面の意思決定 |
| 5.原価計画・低減 |
| 5-1 各部署毎の原価低減内容 5-2 改善の進め方 5-3 原価低減の事例 |
| 6.質疑応答・相談 |