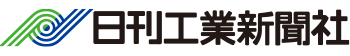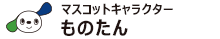セミナー
【会場×ライブ配信セミナー同時開催】
コストミニマムでクレームをゼロにする健全な方法/品質事故 を根っこから根絶する!
「4ゼロ活動」で達成できる!
品質クレーム×不良ゼロへのアプローチ
開催主旨
不良が減るとクレームは減る(最終出荷検査での見逃しも減る)
【クレームゼロ=不良ゼロ×検査の見逃しゼロ×設計ミスゼロ×部 材不良ゼロ】という考え方に則り、それぞれの要因と対策を示し、 具体的な施策を解説します。
そして、これら「4つのゼロ活動」を統合し、万が一クレームが 発生した時にも即応できる、これからの時代の「品質保証体制の整 備」を提案します。この体制は「海外工場の品質マネジメント」に も対応できます。
本セミナーの講師は、2000年当時から「品質事故」という現象に注 目し、その原因の追究と対策をし続けてきました。この知見に基づ き、本セミナーでは品質事故の実態、根本原因と対策を解説し品質 事故の予備群である「クレーム」の根本原因と具体的な対策を実施 してきた事例から紹介します。
「クレームがゼロにならない」いま日本の企業ではどこで品質事故 を起こしても不思議ではない状況に陥っています。危機的状況に陥 る前に「クレームゼロ」を実現し、企業の存続をも脅かす「品質事 故や品質不正」への根を断ちましょう。
【受講対象者】
・品質保証部門、製造、設計、購買の責任者、リーダー
・クレームをゼロにしたい方。不良をゼロにしたい方
・設計ミスをなくしたい方、部材品質を上げたい方
・海外工場の品質を上げたい、クレームをゼロにしたい方
受講特典として、書籍を進呈!
決定版学び直しのカイゼン全書
概要
| 日時 | 2025年 11月 20日(木)10:00~17:00 (9:30 受付開始 休憩60分) ※昼食のご用意がございませんので、ご準備いただくか休憩時間内に外食いただきますようお願い申し上げます。(休憩時間の会場内飲食は可能) |
|---|---|
| 会場 | 【会場またはライブ配信の選択制】 日刊工業新聞社 東京本社 セミナールーム ※会場には受講者用の駐車場が有りません。必ず最寄りの公共交通機関でご来場ください。 ライブ配信 ビデオ会議ツール「Zoom」 ※ブラウザとインターネット接続環境があれば、どこからでも参加可能です。 当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 |
| 受講料 | 48,400円(資料含む、消費税込) |
| 主催 | 日刊工業新聞社
※弊社プライバシーポリシー(個人情報保護方針)をご一読いただき、申込みフォームより必要事項をご入力ください。 |
| 申込について | 受講にあたり 開催決定後、受講票並び請求書をメール(PDFファイル)にてお送り致します。 申込者が最少催行人数に達していない講座の場合、開催を見送りとさせて頂くことがございます。(担当者より一週間前を目途にご連絡致します。) 申し込み方法 各セミナーのお申込みフォームからお申込みいただくか、FAX申込書をダウンロードしご記入のうえ、FAXにてお申込みください。 受講料 振込手数料は貴社でご負担願います。 キャンセルについて 開催日1週間前までの受付とさせて頂きます。1週間前までにご連絡がない場合はご欠席の方もキャンセル料として受講料全額を頂きます。 |
| 申込み締切日 | ライブ配信の申込み締切日 2025/11/17(月)17:00 受付締切 資料のご郵送に伴い、お申込み締切日が早くなります。 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 イベント事業部・事業推進部(名古屋) TEL:052-931-6158 FAX:052-931-6159 E-mail:nk-event@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
| FAX申込について |
講師
会場アクセス
-
日刊工業新聞社 東京本社
セミナールーム
中央区日本橋小網町14ー1
住生日本橋小網町ビル - セミナー会場案内図
プログラム
| 1.品質事故の実態 |
|
1.1 長年不正を続ける企業:不正(故意)、事故(過失) |
| 2.品質保証体制整備へのアプローチ |
|
2.1 今までの品質保証体制 2.3 スピード対応:クレームは全員で対応し、待ち状態が見えるようにして優先順位を決め、1日で回答 |
| 3.検査作業改善へのアプローチ(見逃しゼロ) |
|
3.1 クレームの原因 |
| 4.不良ゼロの9原則 |
|
4.1 原則-1 不良は結果である |
| 5.ルールを守る人づくり |
|
5.1 なぜルールを守らないのか |
| 6.設計ミスゼロへのアプローチ |
|
6.1 設計業務の実態 |
| 7.部材品質不良ゼロへのアプローチ |
|
7.1 従来の品質マネジメントの課題 |
| 8.まとめ |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |