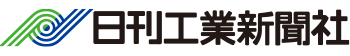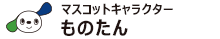セミナー
【ライブ配信セミナー】
精度がでない・予想と違う値がでる・解析モデルに自信が持てない
解析例で学ぶCAE使いこなしのポイント
「材料力学」と「有限要素法」を知ればCAEとはもっと使える
開催主旨
設計者によるCAEの利用は、製品の機能・性能を事前に予測・評価することで設計の精度を向上させ、ひいては後工程での手戻りを削減するメリットがあります。特に近年のソフト・ハードの長足の進歩により、CAEソフトはCADの延長線上で手軽に使えるソフトとなりました。とはいえ、オペレーションがしやすくなることと、解析結果を正しく評価し、設計に活かせることとは別物です。解析結果を解釈し、正しい値がでない場合は、でてくるように自分の道を切り拓いていかなければなりません。それには、現象を材料力学の「目」で見て理解する必要がありますし、「道具」であるソフトがどのような仕組みでできているか、どんな場合には正しい結果が出てこないかを知っておく必要があります。
本セミナーでは、CAE解析で設計者が陥りやすいトラブル例を引きながら、解析モデルの設定から結果の解釈・評価、また設計上の再検討の仕方までを身に着けます。有限要素法や材料力学の知識を紹介しながら、現実世界の現象をどのようにシミュレーションモデルとして再現すればよいのかそのコツを学びます。
受講対象者
設計者、CAE技術者
習得可能知識
1.CAE解析のメカニズムである有限要素法や、材料の挙動の原理原則である材料力学を理解できる
2.シミュレーションモデルや解析結果が妥当か否かを理解できる
3.解析結果からどのような道筋で設計を改善していくかを理解できる
進呈書籍
「材料力学を理解してCAEを使いこなす CAEのよくある悩みと解決法」(水野操著、日刊工業新聞社刊)を進呈致します。
持ち物
筆記用具(シャープペン、消しゴム、黒・赤ボールペン)と電卓をご持参ください。
概要
| 日時 | 2026年 3月 27日(金)10:00~17:00 (9:30 ログイン開始)※昼休憩1時間あり |
|---|---|
| 会場 | WEBセミナー WEBセミナーは、WEBミーティングツール「Zoom」を使用して開催いたします。 ※当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 ブラウザとインターネット接続環境があれば、どこからでも参加可能です。 |
| 受講料 | お一人様:48,400円(資料含む、消費税込) 受講にあたり |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 申込締切日について | 講座開催の3営業日前17:00〆切 ※セミナーによって締切が異なる場合もございます。早めにお申込みください。 原則、資料を受講者の方へ郵送するため、お手元に届く猶予を頂いております。予めご了承ください。 【営業日】について 営業日は平日になります。 ※土曜/日曜/祝祭日は、休業日です。 (例)6/16(火)開催の場合、6/11(木)が締切日となります。 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 事業推進部(セミナー係) TEL: 03-5644-7222 FAX: 03-5644-7215 E-mail : j-seminar@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
| FAX申込について |
講師
プログラム
| 1.あなたの解析結果は、本当に正しいのか? |
| 1) 構造解析初心者からよく聞く悩み |
| 2.自分の使う解析ソフトの仕組みを知ろう~有限要素法の基礎知識 |
| 1) そもそも有限要素法は、どうやって答えを求めるのか 1-1 有限要素法がどんな形にも対応できるのはなぜか~離散化 1-2 分割した要素の一つひとつを「ばね」と考え、それらが集合した対象を「ばね」と考える 1-3 各要素の剛性から物体全体の剛性を求め、さらに各要素の応力や変位を求める 2) 要素選びの判断基準 2-1 要素(メッシュ)の種類 2-2 解析対象が2次元モデルか3次元モデルか 2-3 シェル要素と梁要素 2-4 一次要素と二次要素、それぞれの使い分け |
| 3.片持ち梁を解析してみよう~解析の流れと用語を理解する |
| 1) [解析例]片持ち梁の解析 2) 解析で何を知りたいか、ゴールをはっきりさせる 3) 解析で理解しておくとよい用語:荷重、反力、内力、応力、フォンミーゼス応力、主応力、強度、安全率、変位、ひずみ 4) 片持ち梁の理論解を計算し、解析解と比べてみよう |
| 4.解析結果が正しいか検証しよう |
| 1) なぜ解析解と実験解が合わないのか~解析モデルの妥当性を検証する 2) 現実を再現するキーとなる境界条件の設定~拘束条件と荷重条件 [解析例]両端支持梁の中央に荷重をかけたときの拘束条件 3) アセンブリ製品の解析に必要な接触条件 |
| 5.材料物性値で解析の精度を高める |
| 1) [解析例]極端な薄板を使ったテレビ台の解析 2) 材料転換に向けて、材料物性値を加味した解析をする 3) 材料物性値とは何か ヤング率、ひずみ、ポアソン比、質量密度、降伏強度、最大引張強度、線膨張係数、応力-ひずみ曲線 4) テレビ台の材料転換を検討しよう |
| 6.事例で学ぶ解析トラブルの改善例 |
| 1) 解析結果のどこに注目するか 2) 解析結果の解像度がよくない 3) 応力が際限なく大きくなっていく 4) 解析モデルが非現実的な変形をしてしまう |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |