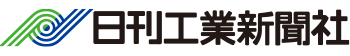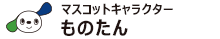セミナー
会場×オンライン開催!録画視聴も可能!
機械の壊れ方で学ぶ実践強度設計
~破壊を防ぐ設計指針の策定から許容応力、安全率の設定法まで~
開催主旨
強度設計は、機械設計者にとっては最重要なテーマです。部材に作用する荷重条件と使用する材料の特性を正確に評価し、疲労破壊の予測と寿命評価が求められます。かつては「軽・小・短・薄」をキーワードに、自動車をはじめとする量産品で軽量化と高強度の両立が求められ、2000年代以降は各種製品・部品の複雑形状化に加え、炭素繊維複合材や高強度鋼など新たな材料が投入されるなど、疲労破壊の予測精度の向上とより正確な寿命評価が必要とされています。これに対応できない結果、2020年代以降、「使用中に安全に機能しない」「使用中に壊れる」といった事情が相次いでいます。
本講座では、「機械の壊れ方」を通じて機械の強度設計で必須となる基礎知識や、設計品質にかかわるモデリング上の設計指針のあり方と許容応力と安全率の設定法を、留意点とともに具体的に解説します。これらの解説内容をもとに、設計品質の向上により疲労破壊に起因する品質不具合を防ぎ、「壊れない機械」「安全に壊れる機械」を生み出す強度設計力を身につけていただきます。
ここ最近は、過去のトラブル事例集をはじめとする社内のナレッジを生成AIで解析・整理することで、ベテランのように不具合の原因を自動的に抽出したり探索したりする取り組みがなされています。ただし“ベテランのように”分析・判定を行うためには疲労破壊の知識の理解を深め実践力をつけることが必須であり、本講座はこれを獲得できる構成となっています。
受講効果
■機械の「壊れ方」を通じて許容応力と安全率の考え方と設定法が学べます。
■破壊を防ぐ設計指針のあり方が理解でき、「壊れない機械」「安全に壊れる機械」の設計につながります。
■生成AIによる過去の破壊事例を解析・整理するための実践力が身につき、ベテランのような分析・判定が可能となります。
本セミナーのテキストは、PDFにてお送り致します。
※お申込みの際に、テキストを受け取れるメールアドレスを記入して下さい(申込アドレスと異なる場合は、申し込みフォームの備考欄にてお知らせ下さい)。
概要
| 日時 | 2025年 11月 25日(火) 10:00~17:00 (9:30 受付開始 休憩60分) ※昼食のご用意がございませんので、ご準備いただくか休憩時間内に外食いただきますようお願い申し上げます。(休憩時間の会場内飲食は可能) |
|---|---|
| 会場 | 会場またはライブ配信の選択制 ライブ配信 ビデオ会議ツール「Zoom」 |
| 受講料 | 46,200円(資料含む、消費税込) |
| 主催 | 日刊工業新聞社
※弊社プライバシーポリシー(個人情報保護方針)をご一読いただき、申込みフォームより必要事項をご入力ください。 |
| 申込について | 受講にあたり 開催決定後、受講票並び請求書をメール(PDFファイル)にてお送り致します。 申込者が最少催行人数に達していない講座の場合、開催を見送りとさせて頂くことがございます。(担当者より一週間前を目途にご連絡致します。) 申し込み方法 各セミナーのお申込みフォームからお申込みいただくか、FAX申込書をダウンロードしご記入のうえ、FAXにてお申込みください。 受講料 振込手数料は貴社でご負担願います。 キャンセルについて 開催日1週間前までの受付とさせて頂きます。1週間前までにご連絡がない場合はご欠席の方もキャンセル料として受講料全額を頂きます。 |
| 申込み締切日 | 2025年11月24日(月)17:00〆切 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 イベント事業部・事業推進部(名古屋) TEL:052-931-6158 FAX:052-931-6159 E-mail:nk-event@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
| FAX申込について |
講師
会場アクセス
-
日刊工業新聞社 東京本社
セミナールーム
中央区日本橋小網町14ー1
住生日本橋小網町ビル - セミナー会場案内図
プログラム
| 1.機械はどう壊れるのか?(代表的な破壊事故) |
| 1-1 空飛ぶタイヤ? 1-2 機械部品の破損原因 1-3 機械部品の破壊事故の原因 |
| 2.強度設計で大切なこと |
| 2-1 機械はなぜ、どのようにして壊れるのか ①航空機用構造部品の192事例/②機械部品470事例/③どのように壊れるのか? 2-2 本講座で得られる強度設計の知識 2-3 製品の破壊を防ぐには ①要求仕様・使用環境条件の明確化/②設計FMEAの活用(具体的数値を提示して解説)/③強度解析と実験の併用/④許容応用と安全率の精度/⑤製品構造体の材料の健全性と品質の確保/⑥過去のトラブル事例の活用/⑦デザインレビューの活用 |
| 3.疲労強度設計手法・プロセス |
| 3-1 破壊形態 ①静的破壊/②衝撃破壊/③疲労破壊/④クリープ破壊/⑤遅れ破壊 3-2 疲労破壊 ①機械材料のき裂/②疲労のき裂/③疲労破壊のき裂進展 3-3 疲労寿命予測 ①S-N線図/②疲労限界線図/③応力拡大係数とき裂進展速度(パリス則) |
| 4.破壊事例を分析・検証①:ターボチャージャーのタービン翼の設計 |
| 4-1 ターボチャージャーとは 4-2 タービン構造 4-3 タービン翼設計の留意点 4-4 タービン翼に印加される力(引張応力・曲げ応力) 4-5 タービン翼の応力解析 4-6 タービン翼の共振 4-7 疲労限界線図 4-8 タービン翼のクリープ特性 4-9 タービン翼破面からの応力推定 |
| 5.破壊事例を分析・検証②:高圧燃料供給システムの設計 |
| 5-1 高圧燃料供給システムとは 5-2 高圧燃料供給システムの低騒音化設計 5-3 同製品の強度設計フロー 5-4 使用環境の明確化 5-5 レールと高圧配管の応力の求め方 5-6 取付状態や振動の影響を受ける部品の応力の求め方 ①高圧配管の取付時に発生する応力/②振動により高圧配管に発生する応力 5-7 高圧燃料供給システムの疲労強度評価 5-8 銅ロー付け部の疲労強度評価 5-9 同製品の不具合事例(現象・原因・対策) |
| 6.壊れない機械のための部品設計指針(講師の経験をもとに) |
| 6-1 応力集中を小さくする形状 ①応力集中率/②応力集中の緩和法 6-2 設計対象の工法を考慮した設計 ①プレス打抜き部品(プレス打抜き部品設計の強度上の問題/プレス打抜き部品設計の指針) ②プレス曲げ部品(プレス曲げ部品設計の強度上の問題/プレス曲げ部品設計の指針 ③ダイカスト品・鋳造品(ダイカスト品・鋳造品設計の強度上の問題/ダイカスト品・鋳造品部品設計の指針) ④プラスチック部品(プラスチック部品設計の強度上の問題/プラスチック部品設計の指針 |
| 7.まとめと質疑応答 |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |