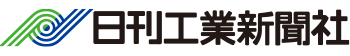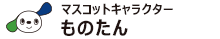セミナー
【会場×ライブ配信セミナー同時開催】
購買担当者の基本と実践
~心構えから実務の基本技法までを徹底解説~
開催主旨
購買部門を取り巻く業務環境はますます厳しくなってきました。
このため購買部門や購買担当者に求められる知識・技能も、ますます多岐にわたりつつあります。
すべての購買担当者のレベルアップが必要な昨今、教育チャンスが少なくむつかしいとされる「新人」「新任」購買担当者の「即戦力化」が大いに必要とされます。
今回棋界の第一人者、大ベテランの野本満雄講師にお願いし、新人・他部門から転籍された新任の皆様に「購買担当者に必要とされる心構えから購買業務知識」を学ぶセミナーを開催することといたしました。
あわせて、もう一度購買の基本を学びたい方、部下の教育を担当されている方、品質・経理部門の方など関係部門の皆様のご参加を是非お勧めいたします。
[受講効果]
①購買担当者としての心構えから購買業務全般の基本が学べます
②値決めの方法や見積書のチェックポイントなど購買コストダウンの手法がつかめます
③知らなかったでは済まされない、独禁法・取適法・契約が具体的事例を含め学習できます
④明日から、やるべきことが明確になります
本セミナーを受講される方には、講師の著書「購買担当者の実務ーコストダウンのための購買業務マニュアル」を当日進呈いたします。
概要
| 日時 | 2026年 3月 10日(火) 10:00~16:30 (9:30 受付開始 休憩60分) ※昼食のご用意がございませんので、ご準備いただくか休憩時間内に外食いただきますようお願い申し上げます。(休憩時間の会場内飲食は可能) |
|---|---|
| 会場 | 会場またはライブ配信の選択制 ライブ配信 ビデオ会議ツール「Zoom」 |
| 受講料 | 48,400円(資料含む、消費税込) |
| 主催 | 日刊工業新聞社
※弊社プライバシーポリシー(個人情報保護方針)をご一読いただき、申込みフォームより必要事項をご入力ください。 |
| 申込について | 受講にあたり 開催決定後、受講票並び請求書をメール(PDF)にてお送り致します。 申込者が最少催行人数に達していない場合、開催を見送りとさせて頂くことがございます。(開催一週間前を目途にご連絡致します。) 申し込み方法 各セミナーのお申込みフォームからお申込みいただくか、FAX申込書をダウンロードしご記入のうえ、お申込みください。 受講料 振込手数料は貴社でご負担願います。 キャンセルについて 開催日1週間前までの受付とさせて頂きます。1週間前までにご連絡がない場合はご欠席の方もキャンセル料として受講料全額を頂きます。 |
| 申込み締切日 | ライブ配信の申込み締切日 2026/3/5(木)15:00 受付締切 ※資料のご郵送に伴い、お申込み締切日が早くなります。 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 イベント事業部・事業推進部(名古屋) TEL:052-931-6158 FAX:052-931-6159 E-mail:nk-event@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
| FAX申込について |
講師
会場アクセス
-
日刊工業新聞社名古屋支社
6階セミナー会場
名古屋市東区泉2-21-28 - セミナー会場案内図
プログラム
| Ⅰ.購買担当者の心構え |
| 1.購買担当者の役割と責務 1)購買管理の目的 2)活動のポイント 2.購買担当者の行動基準 1)購買業務の奥の深さとむつかしさ 2)行動基準とは何か 3.プロの購買担当者3つの条件 4.自己啓発の進め方 |
| Ⅱ.購買業務と関係法律・契約 |
|
1.社内規程と関係法律の遵守 |
| Ⅲ.購買事務手続きと実務上注意すべき事項 |
| 1.購買事務手続きの流れ 2.購買事務手続き簡素化のポイント 3.購買方法の種類 |
| Ⅳ.発注先の選定と日常管理 |
| 1.良い取引先の条件 2.良い取引先を見つける方法 3.取引先の実態を調査する方法 4.格付け評価の実施と結果を取引に反映する方法 |
| Ⅴ.調達品のコストダウン施策 |
| 1.見積価格の妥当性をチェックする方法 1)前値と比較する方法 2)市場相場と比較する方法 3)類似品から類する方法 4)経験的算出方法 5)見積合わせによりレベルを知る方法 6)見積明細書の分析による方法 2.発注テクニックにより価格を引き下げる方法 1)チャレンジする方法はたくさんある 2)ゆさぶりとプロポーズの使い分け 3.値下げ交渉の進め方 1)駆け引きより説得力 2)値下げ交渉10の心得 3)質問の活用 4)値下げの申し入れ方法 5)折衝場所への配慮 6)その他 4.値上げ要請への対応策 |
| Ⅵ.納期確保の技術 |
| 1.納期管理の目的 2.納期管理の考え方と具体的対策 3.納期遅延別対応策 |
| Ⅶ.適正品質を確保する技術 |
| 1.請求元要求品質のチェック 2.取引先が理解できているか、理解できる仕様になっているかチェック 3.取引先品質管理体制の審査・確認 4.品質保証契約の締結と品質責任者の登録 5.必要に応じ品質不良による損害賠償の請求と交渉 |
| Ⅷ.まとめと質疑 |