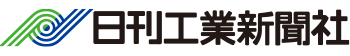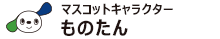セミナー
【ライブ配信&後日の録画視聴可】
製造業事業者が知っておくべき
工場の排水に関する法規制と対応実務
~水質汚濁防止法、下水道法、浄化槽法の規制内容からPFAS対策、コスト削減に繋がる最新の排水処理技術まで、実務に役立つ知識を徹底解説~
開催主旨
水環境の保全は、企業にとって社会的責任であると同時に、法令遵守(コンプライアンス)が厳しく問われる経営リスクの一つです。
我が国には、水質汚濁防止法、下水道法、浄化槽法など、工場・事業場の排水に適用される法規制が多岐にわたり存在します。しかし、「自社に適用される法律が何か」「法律をどう解釈し、実務でどう対応すべきか」を体系的に把握されている方は、決して多くありません。また、排水処理設備のコスト削減や効率化、最新技術による水質改善に課題を抱え、どこから着手すべきか見当がつかないという声も多く聞かれます。本講座は、まさにこうした課題を持つ製造業の皆様を対象としています。
また、本講座は、工場・事業場の排水に適用される水質汚濁防止法、下水道法、浄化槽法などの主要な法令について、その規制内容、事業者としての責務、そして違反時の罰則までを体系的にわかりやすく解説します。単なる知識の羅列ではなく、具体的な事例を交えながら、自社がどう動くべきか、実務に直結する解釈法と対応策を学べます。
さらに近年、水質汚染が問題視され、水道法上の暫定目標値が定められるなど、規制動向に注目が集まるPFAS(有機フッ素化合物)などの最新の話題についても、その概要と動向を詳しく説明します。
この機会に、法令違反による罰則・社会的信用の失墜というリスクを回避するため、曖昧だった法規制を明確に理解し、排水処理の課題解決と環境負荷低減を確実に取り組むための知識を習得しましょう。
受講対象
■工場・事業場の環境コンプライアンスを徹底したい経営者・管理部門の担当者
■排水処理設備・水関連設備の管理/保守・維持管理を担当されている方
■水質関連の法令(水質汚濁防止法など)を体系的に学び、リスク対応力を高めたい方
■排水処理のコスト削減や効率化、最新技術の導入を検討されている方
習得可能知識
■世の中の水の循環構造と、各種法令の目的・解釈
■水質汚濁防止法・下水道法・浄化槽法など、主要法令の具体的な規制内容と違反時の罰則
■BOD、SS、COD、窒素、りんなど、主な汚染物質に対する処理技術の仕組み・特徴
■工場の節水・水再利用事例と、課題解決のためのヒント
■PFASをはじめとする最新の環境規制動向と水質基準の概要
本セミナーは、オンライン形式でのセミナーとなります。オンラインでのご視聴方法(参加用URL等)はご登録くださいましたメールにお知らせいたします。ZOOMでの視聴が困難な方には別途、こちらの手順を参照のうえブラウザ上でご視聴ください。
概要
| 日時 | 2026年 2月 3日(火)13:00~17:00 ※開催当日12:00まで申込受付 |
|---|---|
| 受講料 | 38,500円(テキスト代、録画視聴、税込、1名分) ※テキストはメールでお知らせします。 ※振込手数料は貴社でご負担願います。開催決定後、受講料の請求書(PDF)ををメールでお知らせします。 ※当日の参加が難しい方は録画での参加も可能です。録画での参加を希望される方は、申込フォームでご選択ください。 ※録画視聴は当日参加された方も講座終了後10日間にわたりご視聴いただけます。 |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 問い合わせ先 | 日刊工業新聞社 西日本支社 総合事業本部 セミナー係 TEL : 06-6946-3382 FAX : 06-6946-3389 E-mail : seminar-osaka@media.nikkan.co.jp |
講師
プログラム
| 1.水質関連法令の全体像と目的 |
| 1-1 世の中の水の流れと循環:水の循環構造を大局的に捉えて 1-2 水質関連の各法律の目的とその背景:知っておきたい法律のポイント 1-3 環境基本法が定める水質関係の環境基準:環境法の「憲法」としての役割 1-4 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律:事業者に定められる責務と公害防止管理者の選任 |
| 2.主要な排水関連法令の規制内容と実務 |
| 2-1 水質汚濁防止法:公共用水域(川や海など)への排水規制の要 ①「排水基準」と都道府県による「上乗せ基準」 ②特定施設、有害物質の定義と排水基準の適用フロー ③事業者に課せられる責務(届出、測定・記録、事故時の対応)と違反時の罰則 2-2 下水道法:下水道へ排水する際の規制と基準 ①排除基準と除害施設の設置義務 2-3 浄化槽法:浄化槽の構造、管理者設置義務と法定検査 2-4 工業用水法(地下水関係):地下水の水源保全と地盤沈下防止 |
| 3.排水処理技術の基礎と応用 |
| 3-1 各種排水処理技術の概略と用途:処理技術の全体像 3-2 物理的・化学的処理のメカニズムと用途:ろ過、凝集沈殿、イオン交換、中和など 3-3 生物学的処理のメカニズムと用途:活性汚泥法、生物膜法、嫌気/好気処理など ①窒素・りん除去技術の仕組み(化学的・生物学的) |
| 4.最新の話題とコスト削減に繋がる実務 |
| 4-1 最新の水質に関する話題:PFASの概要と規制動向 4-2 排水処理技術を応用した工場の節水事例 ①排水の再利用による水使用量低減の事例(ボイラドレン、雑排水利用など) ②地下水の水質改善事例(鉄バクテリア法) ③膜分離活性汚泥法 (MBR):設備小型化と水質改善 |
| 5.さいごに |
| 5-1 さまざまな水の水質に関する基準:工業用水、冷却水、ボイラ水などの基準 5-2 質疑応答と総括、全体のまとめ |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |