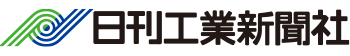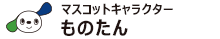セミナー
【設計通りに装置が動かない?】
現場で進める簡易自動化・からくり設計に役立つ機構設計のキホン
~からくり設計を【期待通りに動かす】ための機構・設計のポイントを学ぶ~
開催主旨
エネルギーの消費を抑え、安価に自動化を実現する「からくり設計」を学ぶ設計者は少なくありません。
しかし、本やネットを利用していろいろな機構やしくみを知る設計者は増えても、からくりを使った治具や装置を期待通りに設計し、動かすことができているでしょうか。
近年、【工学知識はしっかり勉強しているけれど、実際に動く装置が設計できない】という設計者が増えてきています。工学計算だけでは動く機構の設計は成り立ちません。
さらに、どこに注目して設計していけば実現できるのか、迷ってしまう設計者も多いのではないでしょうか。
作ったはいいが、思ったような動きにならなかったり、途中で壊れてしまったり。
はたまた対策を講じようとしても、どこが悪いかわからない、指摘できない、予算を大幅にオーバーする…
…知識としてからくりを知っていても、具現化できなければ意味がありません。
からくり設計を【期待通りに動かす】ためには、工学計算に加えて、機構の理解・設計力がとても重要です。
動く機構の設計ができないと、せっかくのからくりも知識も宝の持ちぐされです。
周りにベテランの設計者がいれば、ノウハウを教えてもらうことも出来るかもしれませんが、そういうベテランのいる現場すら減ってきています。
しかも、設計力は、書籍や独学だけではなかなか身につくものではありません。
本講座では、簡易自動化・からくり設計を実現するために機構を設計する際の構造に関する知識や、注意すべきポイントを押さえ、直接、理論的かつ経験的に見ていきます。
機構設計していても、「設計にいまひとつ自信が持てない」「方向性に迷う」「どこに注目して設計を始めたらいいかわからない」と不安を感じている機械設計者や、機械はわかるがさらに自信をつけたい設計者、からくり設計のおさえるべきポイントを知りたい方々に最適の講座です。
現場の設計者に”生きた設計力”を身に着けさせるため、からくり設計について、実務に近い、さらに一歩突っ込んだ解説を加えます。
概要
| 日時 | 2026年 1月 20日(火) 10:00~17:00 (9:30 受付開始 休憩60分) ※昼食のご用意がございませんので、ご準備いただくか休憩時間内に外食いただきますようお願い申し上げます。(休憩時間の会場内飲食は可能) |
|---|---|
| 会場 | 日刊工業新聞社名古屋支社 6階セミナー会場 ※会場には受講者用の駐車場が有りません。必ず最寄りの公共交通機関でご来場ください。 ※当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 |
| 受講料 | 46,200円(資料含む、消費税込) |
| 主催 | 日刊工業新聞社
※弊社プライバシーポリシー(個人情報保護方針)をご一読いただき、申込みフォームより必要事項をご入力ください。 |
| 申込について | 受講にあたり 開催決定後、受講票並び請求書をメール(PDF)にてお送り致します。 申込者が最少催行人数に達していない場合、開催を見送りとさせて頂くことがございます。(開催一週間前を目途にご連絡致します。) 申し込み方法 各セミナーのお申込みフォームからお申込みいただくか、FAX申込書をダウンロードしご記入のうえ、お申込みください。 受講料 振込手数料は貴社でご負担願います。 キャンセルについて 開催日1週間前までの受付とさせて頂きます。1週間前までにご連絡がない場合はご欠席の方もキャンセル料として受講料全額を頂きます。 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 イベント事業部・事業推進部(名古屋) TEL:052-931-6158 FAX:052-931-6159 E-mail:nk-event@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
| FAX申込について |
講師
会場アクセス
-
日刊工業新聞社名古屋支社
6階セミナー会場
名古屋市東区泉2-21-28 - セミナー会場案内図
プログラム
| 1. 【からくり設計】で期待通りに【動かない要因】 |
| 1-1 そもそも機構の選択は何を基準に決めたのか 1-2 作った後で出てきた問題。作る前に問題が把握できない原因は? 1-3 問題点はどこ? 1-4 検討時に見落としたところは? |
| 2. からくり設計の概要 |
| 2-1 からくり機構の種類 2-2 からくり機構でできること 2-3 からくり機構の「ネットや本では解説されないポイント」 |
| 3. からくり設計での機構設計のキホン |
| 3-1 てこの原理は知っていて使う 3-2 動力伝達構造での設計はここに注意 3-3 すべる部分と摩耗する部分の発見で摩耗防止 3-4 からくりに使われる基本的な部分 |
| 4. 機構の構造を知り、からくりの選定力を養う |
| 4-1 からくりに何が要求されるのか、機構設計に何が必要か 4-2 見落としがちな設計ポイントはどこか 4-3 構造は基本部分のさらに基本が大切 |
| 5. 構造設計の注意点を知って、からくり機構を使おう |
| 5-1 支点部分の設計の注意点 5-2 形状を決める注意点 5-3 構造物の設計を決める注意点 |
| 6. 機構の設計はこうすれば生きてくる |
| 6-1 からくりを【期待通りに動かす】ための知識 6-2 動く部分に必要なことは計算だけでは出てこない、知らなければ出てこない 6-3 気が付かなければいけないところはどこか注目する(演習) 6-4 気が付かなくて起きたこと(演習) 6-5 優先順位と選択を考える 6-6 精度面、加工性、コストから構造を考える 6-7 設計ポイントを別の機構に応用する際の重要点 |
| 7. からくり設計を治具化、自動化へ応用を検討するためのポイント |
| 7-1 からくり機構から治具へ、装置へ、移行するために 7-2 設計の正解はひとつではない 7-3 ひとりよがりはだめ~最適な機構設計が大事~構造による差を考えよう 7-4 実践演習 |