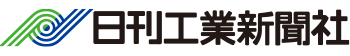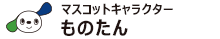セミナー
【ライブ配信セミナー】
プロセスチャートで手順を確認!
システムズエンジニアリングの手順とポイント
~狙った機能/性能がでない・開発が複雑化し収拾がつかない・設計変更で手戻りが多発する~
開催主旨
複雑で高度な制御が必要となる昨今のメカトロ製品。最近ではネットワーク対応が進むなどシステム(製品)の複雑化・大規模化が進んでいます。こうしたシステムの開発ではメカ・エレ・ソフト各部門の連携が必須ですが、それぞれ文化の違いから検討の抜け落ちなどが多発し、結果として「ニーズを外したパッとしない製品になる」「組付けたものの狙った機能・性能がでない」「後工程で設計変更を余儀なくされた」などといった事態に発展しています。システムズエンジニアリングは、ステークホルダ(システムの使い手や作り手など)の声を起点にシステムが具備すべき機能を段階的に具体化して仕様に落とし込んでいく手法です。開発にかかわる全員が同じ言葉で同じ情報を共有しながら仕様を煮詰めていくため後工程で余計な干渉をうけることなく確実に狙いのシステムへと導きます。
本セミナーでは、システムズエンジニアリングの進め方を工程ごとにフローチャートで示し、それぞれで何を検討し、取り決めていくべきかを学びます。実際のメカトロ製品(業務用プリンター)を例に実務に即した分野横断的な連携力を強化していきます。近年、製造業では業務の細分化が進み、システム全体を一貫して設計・構築する機会が減少しているため、製品開発を俯瞰的に捉えられる人材が不足しています。システムズエンジニアリングをこうした人材を養成する場としても優れています。
受講対象者
ものづくりに携わる技術者全般、特にメカ・エレキ・ソフトなど複数分野にまたがる製品設計に携わる技術者
習得可能知識
・システムズエンジニアリングの基本プロセスと実務上のプロセス
・メカ設計、回路設計、制御設計が連動した効率的な開発
・フロントローディングを実現し、後工程での設計変更の撲滅
・狙った機能・性能を作り込むことによる付加価値の最大化
進呈書籍
参考図書:『システムズエンジニアリングに基づく 製品開発の実践的アプローチ』を進呈致します。
概要
| 日時 | 2026年 2月 13日(金)10:00~17:00 (9:30 ログイン開始)※昼休憩1時間あり |
|---|---|
| 会場 | WEBセミナー WEBセミナーは、WEBミーティングツール「Zoom」を使用して開催いたします。 ※当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 ブラウザとインターネット接続環境があれば、どこからでも参加可能です。 |
| 受講料 | お一人様:48,400円(資料含む、消費税込) 受講にあたり |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 申込締切日について | 講座開催の3営業日前17:00〆切 ※セミナーによって締切が異なる場合もございます。早めにお申込みください。 原則、資料を受講者の方へ郵送するため、お手元に届く猶予を頂いております。予めご了承ください。 【営業日】について 営業日は平日になります。 ※土曜/日曜/祝祭日は、休業日です。 (例)6/16(火)開催の場合、6/11(木)が締切日となります。 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 事業推進部(セミナー係) TEL: 03-5644-7222 FAX: 03-5644-7215 E-mail : j-seminar@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
| FAX申込について |
講師
プログラム
| 1. 複雑化する製品開発とシステムズエンジニアリングの重要性 ~製品開発の複雑化と開発者の悩み |
| - 受講者ワーク(10分): 製品開発でうまくいっていないこと、強化したいポイントを書き出し、数名が発表(個人ワーク) - システムズエンジニアリングとは - システムズエンジニアリングの歴史 - CASE、IoT/DXがもたらす開発環境の変化 - システムズエンジニアリングの基本概念と適用メリット - システムズエンジニアリングの実践に必要なプロセスチャート - 質疑応答(5分) |
| 2. ステークホルダ要求分析とシステム要求定義の基礎 ~ステークホルダの声から具体的なニーズを引き出す |
| - 製品開発あるある①:大規模プロジェクトが空中分解する原因とは? - ステークホルダ要求定義、システム要求定義プロセスの全体像 - ステークホルダの声を集める(利害関係者の特定と関係性マッピング) - ステークホルダのニーズ分析(真のニーズの抽出) - ステークホルダ要求の定義と目標値の決め方 - システム要求定義の詳細解説(要求の文書化・管理方法など) - 質疑応答(5分) |
| 3. システムの構造を決める アーキテクチャ設計 ~システムで実現すべき機能・構造を突き詰める |
| - 製品開発あるある②:個別最適にまっしぐら、木を見て森を見ないアーキテクチャ設計(AI事例) - システムアーキテクチャ設計プロセスの全体像 - 論理アーキテクチャと物理アーキテクチャの理解 - 論理アーキテクチャ設計(機能分解、統合、最適化) - 物理アーキテクチャ検討(機能割当、物理境界、トレードオフ、検証) - メカ・エレキ・ソフトのインタフェース定義と管理(抽出、管理文書) - 質疑応答(5分) |
| 4. メカ・エレキ・ソフトの協調開発を実現するために ~システムズエンジニアリング成功の条件 |
| - 受講者ワーク(10分): 協調開発で起こりうる問題や課題をリストアップし、数名が発表(個人ワーク) - 協調開発の現状と課題 - メカ・エレキ・ソフト分野間の開発文化や言語の違い - 現場でよく起こる認識齟齬や手戻りの具体例 - 協調開発の重要性と困難さの背景 - 協調開発を促進するためのプロセス設計のポイント - 目的と手段の分離 - 製品開発は竪堀ではなく、露天掘り(全体を俯瞰した進め方) - 常に成立していることを確認する重要性 - 振る舞いと構造を可視化してインタフェースを明確にする - 役割と責任範囲の明確化 - 具体的事例で学ぶ、メカ・エレキ・ソフト協調設計 - 産業用プリンタ開発の事例 - AIシステム開発の事例 - イノベーションテーマにおける協調開発事例 - 質疑応答(5分) |
| 5. まとめと質疑応答 |
| - 受講者ワーク(10分): セクション1で挙げた自部門の課題に対して、本セミナーで学んだ内容をどう活用できるかをまとめ、数名が発表(個人ワーク) - 本日の振り返り - 今後の適用に向けてのポイント - 総合質疑応答 |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |