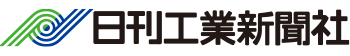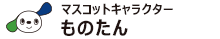セミナー
【ライブ配信&後日の録画視聴可】
後工程のムダ・手戻りをゼロに!機械設計の新常識
プロが徹底指南!
設計意図が正しく伝わる機械図面の作法と実践
~具体的な事例で学ぶ!製造・組立・メンテ部門が「ナットク!」する設計~
開催主旨
「その図面じゃ、作れないよ!」「なんでこんなに組みにくいんだ!」 製造、加工、組立、そしてメンテナンス部門など、後工程の方々から、こうした"クレーム"や"困惑の声"を投げかけられた経験はありませんか?
設計意図が正しく伝わらない図面は、手戻り、コスト増、納期遅延の直接的な原因となり、設計者の評価を下げるだけでなく、プロジェクト全体の非効率を生み出します。
特に近年、3Dモデルベース開発(MBD/MBE)への移行や、設計・製造プロセスにおけるDX化が加速する中、「図面を描く」という行為の意味合い自体が変化しています。従来の「バラシ(詳細設計・図面化)」に多くの時間をかける設計者の存在意義は問われ始めています。
本講座では、機械設計・機構設計のプロが、自身の豊富な経験に基づいた「後工程を困惑させた設計あるある」と、その具体的な「改善事例」を徹底解説します。
単なる製図法の復習ではなく、「作りやすさ(DfMA)」や「メンテナンス性(DfM)」までを見据えた、上流から下流まで一気通貫で通用するワンランク上の設計思想と図面作成のコツを伝授。参加いただいた方の課題に応じてより適した事例も追加で紹介し、検図の進め方についても、講師独自の視点で言及いたします。
新人・若手指導に当たる中堅技術者はもちろん、「自分の設計は本当にこれでいいのか?」と自問する中級者以上の設計者にも最適です。
本講座を通じて、「不確実な設計」や「後工程に負荷をかける設計」から脱却し、これからの時代に求められる真のプロフェッショナルな機械設計者への進化を目指しましょう。
習得可能知識
■製造・組立・メンテ部門からの手戻り・クレームを激減させ、工期遅延とコスト増を防ぎます。
■DfX(製造容易性・組立容易性)を体得し、設計者としての市場価値を高めます。
■「バラシ・検図」の非効率から脱却し、DX時代に求められる設計思考を習得できます。
■若手・新人への指導レベルを底上げし、設計部門全体の品質と技術継承を促進します。
本セミナーは、オンライン形式でのセミナーとなります。オンラインでのご視聴方法(参加用URL等)はご登録くださいましたメールにお知らせいたします。ZOOMでの視聴が困難な方には別途、こちらの手順を参照のうえブラウザ上でご視聴ください。
概要
| 日時 | 2026年 5月 25日(月)13:00~17:00 ※開催当日12:00まで受付 |
|---|---|
| 受講料 | 39,600円(テキスト代、録画視聴、税込、1名分) ※テキストはメールでお知らせします。 ※振込手数料は貴社でご負担願います。開催決定後、受講料の請求書(PDF)ををメールでお知らせします。 ※当日の参加が難しい方は録画での参加も可能です。録画での参加を希望される方は、申込フォームでご選択ください。 ※録画視聴は当日参加された方も講座終了後10日間にわたりご視聴いただけます。 |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 協力 | 株式会社ウズラ技研 |
| 問い合わせ先 | 日刊工業新聞社 イベント事業本部 西日本支社 セミナー担当 TEL : 052-931-6158 E-mail : seminar-osaka@media.nikkan.co.jp |
講師
プログラム
| 1.製図編:後工程の手戻りを誘発する図面あるある 〜誤解ゼロの図面表現技術 |
|
1-1 公差指示の「過剰品質・過剰精度」を防ぐ鉄則(例:不要な桁数と厳しい公差) |
| 2.材料・加工編:後工程が「作れない!」と叫ぶ加工あるある 〜DfM(製造容易性の設計)の実践 |
| 2-1 溶接ビードを無視した「干渉部品形状」の設計ミスと改善策 2-2 曲げ部品における「曲げ部と穴の近接」による変形対策 2-3 「板厚・タップ径の不適合」によるねじ強度不足の回避 2-4 【実践】 設備制約を無視した「深すぎる曲げ」の設計 2-5 「溶接トーチのクリアランス不足」:溶接不可設計からの脱却 2-6 「異種金属溶接」や「熱処理と材料の矛盾」によるトラブル 2-7 加工段替えを最小化する「一面加工基準」の設計思想 2-8 「測定できない点を基準とした寸法公差」の無効性 2-9 「ケンカする設計」(逃げがない部品の組み合わせ)の回避 2-10 角パイプ中央のリブ:「溶接による変形」リスクの予見 2-11 製缶品における「水抜き穴・通気穴」の重要性と指示 2-12 勝手違い部品の図面:「単純ミラーリング」の罠と展開方向の考慮 2-13 市場規格(3×6・4×8・5×10等)を意識した材料取り 2-14 「材料取りのムダ」をなくす形状設計 2-15 製缶品における「加工精度が必要な面へのマスキング指示」の徹底 |
| 3.組立編:後工程が「組みにくい!」と怒る組立図面あるある 〜DfA(組立容易性の設計)の徹底 |
| 3-1 「数mm違いの類似部品」による組立ミス・判別工数を削減する設計 3-2 高精度要求部品の「再現性」を確保する基準当て・ノックピン設計 3-3 「ボルトサイズの統一化」による工具交換・在庫ムダの削減 3-4 「サブASSY」可能な多ユニット構成とベース設計の重要性 3-5 組立基準はセンターより端面が基本!その理由と適用 3-6 「シム調整時の分解工数」を減らす構造設計 3-7 「取り外し・メンテナンス」を考慮した抜きタップ・サービス空間 3-8 ラック&ピニオン構成における「ラック下向き」の設計リスク 3-9 テンション調整機構における「真っ直ぐ押し引きできる構造」の設計 3-10 「目視不可」な設計(例:減速機のオイルレベル)と改善策 |
| 4.調整・据付:後工程が「設置・メンテできない!」と叫ぶあるある 〜LCC(ライフサイクルコスト)を意識した設計 |
| 4-1 配線を無視した「ベースの配線穴不足」対策 4-2 「LMガイドレールのタイトな溝嵌め」による組付け難易度の上昇 4-3 アンカー種類を考慮しない「アンカーブラケット設計」の失敗 4-4 LMガイドにおける「ブロック・レールの基準の不統一」 4-5 「多種類の工具が一度に必要な取付」を避ける設計 4-6 搬送・搬入を考慮した「設備サイズ・分割」の事前検証 4-7 重量物への「吊りタップ・吊り箇所」の必須設計 4-8 徹底した「グリスアップ・給油・点検」を可能にする構造 4-9 ウレタンローラなど「長時間姿勢維持による扁平」を防ぐ搬送・保管設計 4-10 トラブル時の「メンテナンス性」を意識した設計 |
| 5.設計:「不確実性」を排除する「だろう設計」からの脱却 |
| 5-1 フランジ穴配置における「強度的な配慮」(十字配置の回避など) 5-2 「自重頼り・だろう設計」を排し「なぜ?」に答える設計思考 5-3 エンドロックシリンダの「全ストローク使用」設計のリスク 5-4 エアシリンダ「オートスイッチの調整・配線」容易性の確保 5-5 フローティング機構の垂直使用 5-6 「無意味なオーバーハング設計」による剛性・振動問題 5-7 【基礎の見直し】 軸受の嵌め合いにおける「すべてすき間ばめ」の危険性 5-8 エア機器のバルブが「立て向き」になっている場合の課題 5-9 オイルパンにおける「ドレンの設計不備」 5-10 近接センサが「上向き」になっている場合の課題 5-11 歯車の「位相調整」を可能にする設計 5-12 「調整がトレードオフ」になる構造の回避 5-13 「ボルト長さ」を無視した設計ミス 5-14 強度計算における「経路途中の応力」検討の重要性 5-15 設計の基本:「最大動作範囲」での検討徹底 |
| 6.検図編:工程のムダをゼロにする「品質の門番」としての検図徹底術 |
| 6-1 検図の種類と役割分担:設計者・製図者の役割と、それぞれの着眼点 6-2 検図の重要性:ノーチェック図面が引き起こす手戻り・コスト増リスクと、品質確保のための原則論 6-3 設計者による検図:「仕様・タクトタイム」を満たしているかの最終確認 6-4 設計者による検図:「機械的強度」の再検証 6-5 設計者による検図:「組立・搬送・据付」の容易性確認 6-6 製図者による検図:「基本情報」の徹底確認 6-7 製図者による検図:「取付部品同士の整合性」確認 6-8 検図の方法①:「網羅型チェックリスト」のメリット・デメリットと、現実的な運用の考え方 6-9 検図の方法②:「属人化する個人の裁量検図」の危険性と、組織としての品質統一の課題 6-10 検図の方法③:「マスト項目リスト」による品質統一と、個人の判断を組み合わせる現実解 6-11 【講師推奨】最適な検図体制:マストリストと教育による品質コントロールの実現 6-12 「最低限これだけは」設計者・製図者が担保すべき最優先チェック項目 |
| 7.質疑応答(機械設計にかかる疑問への回答)とこれからの設計者の役割 |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |