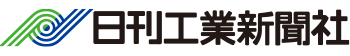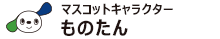セミナー
【ライブ配信&後日の録画視聴可】
3Dプリンタ×デジタルツインセミナー
DfAM実践のための設計プロセス革新と
超低コストで始めるデジタルツイン活用
開催主旨
【前半:3Dプリンタ】
ワールドワイドでの産業用3Dプリンタ(付加製造(AM)装置)市場は、2026年にかけて年平均成長率20.0%で推移し、市場規模が大幅に拡大すると言われています 。モノづくり現場で期待される導入効果は、「コスト削減」「リードタイム短縮」「在庫管理の簡略化」であり 、特に治工具の内製化や、対象物に応じて設計・製作する適用例が増大しています。
しかし、3Dプリンタの真価を発揮するには、単にデータを出力するだけでなく、従来の設計手法にとらわれない新世代の機械設計が不可欠です。すなわち、AMの特性を最大限に活かし、弱点を補強するための設計思想、DfAM(付加製造のための設計)の習得が求められます。
本講座では、AMの特徴を捉えた設計の考え方であるDfAMを核とし、特に近年の設計プロセスを革新している最新の形状最適化技術に焦点を当てます 。具体的には、与えられた条件から最適な軽量構造を導き出すトポロジー最適化 、そして複数の製造方法や材料の制約を考慮し、AIが多様な最適形状案を提案するジェネレーティブデザイン の原理、活用プロセス、および実践的な事例を詳解します。
本講座を通じて、3Dプリンタの基礎知識と造形プロセスの勘所を再確認しつつ、DfAMの思想に基づき、トポロジー最適化やジェネレーティブデザインといった最新ツールを駆使して、AMの真の力を引き出す設計・部品形状のヒントを掴みましょう。これにより、開発現場で成果を上げる新世代の機械設計と設計プロセスへの転換を強力に支援します。
【後半:デジタルツイン】
製品開発の現場において、「試作してみないと分からない」「後工程で不具合が見つかり、手戻りが発生する」といった課題は依然として深刻です。こうした課題解決の鍵となるのが、バーチャル空間で検証を完結させる「デジタルツイン」の考え方です。
「デジタルツイン」と聞くと大規模なシステム投資を想起しがちですが、実は設計者が日常的に扱う3DデータやBOM(部品表)の連携から、コストをかけずにスモールスタートで始めることが可能です。
本講座では、1時間半の凝縮したプログラムで、CAE(解析)、BOM、アニメーションを活用した具体的な検証プロセスを解説します。設計初期(フロントローディング)での精度向上、試作回数の削減、そして全部門へのデータ連携まで、「今の業務にどう組み込むか」という実践的な視点で、開発プロセスの変革ステップを紐解きます。
受講対象
□従来の設計手法にとらわれない、新しい設計アプローチを模索している機械設計エンジニア
□3Dプリンタを導入済みだが、「試作」止まりで「実部品・治具」への活用が進んでいない生産技術・設計担当者
□軽量化・高強度化を実現する「トポロジー最適化」や「ジェネレーティブデザイン」の具体的実践法を学びたい方
□治工具の内製化やマスカスタマイゼーションによるコスト削減・リードタイム短縮を実現したい現場リーダー
■「後工程での手戻りが多い」など課題を抱える開発・設計の実務担当者(機械、エレキ、組み込み等)
■デジタルツインやDXに興味はあるが、高額なシステム投資は難しく、身近なツールでスモールスタートしたい部門責任者
■設計BOMと3Dデータの連携、CAE活用により、設計初期(フロントローディング)で品質を作り込みたいリーダー・マネージャー
■製造部門や他部署との合意形成をスムーズにしたい方
習得可能知識
□DfAMの習得: 単なる「置き換え」ではなく、3Dプリンタの特性を最大限に活かし、弱点を補う設計思想が身につきます。
□最新最適化ツールの実践的活用: AIを活用した「ジェネレーティブデザイン」や「トポロジー最適化」の原理を知り、実務での軽量化・高性能化への適用プロセスを理解できます。
□造形プロセスの勘所と失敗回避: 材料特性、造形方式の選定、サポート材除去や後加工までを含めた「製造全体」を考慮した設計データ作成のコツを習得できます。
□コスト対効果の最大化: AM(付加製造)とSM(除去加工)の使い分けやハイブリッド活用の視点を持ち、開発全体のコストパフォーマンスを高める判断ができるようになります。
■コストをかけないデジタルツインの構築:PC内で検証を完結させる手法を習得できます。
■「試作レス」開発へのロードマップ:物理的な試作回数を劇的に減らす具体的なフローが描けるようになります。
■手戻りゼロを実現するデータ連携:設計変更時の影響範囲を即座に把握し、人的ミスや伝達漏れを防ぐ管理手法が身につきます。
■視覚的な合意形成力:静止画では伝わりにくい「動き」や「干渉」を動画で可視化し、製造現場や他部門と直感的なコミュニケーションが可能になります。
本セミナーは、オンライン配信ツールZoomを使い、出演者自身も自宅から出演いただく形式の「Home to Home」(H2H)セミナーとなります。ご視聴方法(参加用URL等)はご登録くださいましたメールにお知らせいたします。
概要
| 日時 | 2026年 2月 17日(火) 13:00~17:00 |
|---|---|
| 受講料 | 39,600円(テキスト代、録画視聴、税込、1名分) ※テキストはメールでお知らせします。 ※振込手数料は貴社でご負担願います。開催決定後、受講料の請求書(PDF)ををメールでお知らせします。 ※当日の参加が難しい方は録画での参加も可能です。録画での参加を希望される方は、申込フォームでご選択ください。 ※録画視聴は当日参加された方も講座終了後10日間にわたりご視聴いただけます。 |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 協力 | いわてデジタルエンジニア育成センター 神上コーポレーション株式会社 |
| 問い合わせ先 | 日刊工業新聞社 西日本支社 総合事業本部 セミナー係 TEL : 06-6946-3382 FAX : 06-6946-3389 E-mail : seminar-osaka@media.nikkan.co.jp |
講師
プログラム
| □解説1(13:00~15:20) |
| 「3Dプリンタ時代の新常識!実践設計と最新形状最適化のコツ〜DfAMを核とした機械設計プロセスとトポロジー最適化・ ジェネレーティブデザイン〜」(講師:いわてデジタルエンジニア育成センター センター長 小原 照記 氏) |
| 1.3Dプリンタ活用のための必須基礎知識 |
| 1-1 AMの基礎と活用の潮流 ①3Dプリンタ(RP)からAM(付加製造)への定義の変化 ②モノづくり現場で期待される導入効果 ③試作検証から治工具の内製化、最終製品への適用拡大 1-2 AMで効果的な製品・用途 ①特に効果が高い製品例:治工具類、マスカスタマイゼーション ②AMの特徴を活かした設計のポイント:一体化設計、ラティス構造 1-3 設計者が知っておくべき主要造形方式と材料特性 ①主要な造形方式(MEX、VPP、PBFなど)の概要と原理 ②各方式のメリット・デメリット |
| 2.DfAM実践のための3Dデータ準備と造形プロセス |
| 2-1 DfAMに必要な3Dデータ作成とファイル形式 ①3Dデータの作成源 ②標準ファイル形式(STL)の構造と課題 ③最新のファイル形式の動向と機能 2-2 DfAM実践に向けた造形設定の勘所 ①スライサーソフトの役割と主な設定項目 ②積層ピッチと充填率の設計品質とコストへの影響 ③造形シミュレーションの活用 2-3 サポート材と積層方向の決定 ①サポート材が必要な形状と、除去が困難な設計上の課題 ②積層方向の検討:強度重視、形状重視、コスト重視のトレードオフ 2-4 造形後の「後加工」の必要性とDfAM ①造形方式ごとの表面性状と後処理の必要性 ②特に金属AMにおける後加工を前提とした設計(DfAM) |
| 3. DfAMと最新設計最適化技術の活用 |
|
3-1 DfAMの基本思想と「弱点補強」のための設計指針 |
| 4. 開発現場で成果を上げる実践的活用と課題解決 |
| 4-1 失敗しない!AM機導入の判断軸とレーダーチャート活用 ①導入検討における注意点 ②導入選定の6つのポイントとレーダーチャートによる比較検討 4-2 現場の不具合事例に学ぶ造形安定化の対策 ①安価なMEX方式で起こりやすい不具合例 ②不具合への具体的な対策 4-3 造形サービス利用におけるデータ作成ルール ①3Dプリンタ出力サービスの利用手順 ②造形方式ごとのデータ作成ルールの理解 4-4 AMの真価!プロセス全体でのコストパフォーマンス向上事例 ①製造個数と形状の複雑さから見るAMの活用領域 ②プロセス全体での効果事例 4-5 AM活用を推進する「設計人材」育成の視点 ①3Dプリンタ単体ではなく、ものづくり全体を視野に入れた活用 ②課題解決に向けたアプローチ:構造最適化ソフトの活用、ハイブリッドな活用 |
| 5. 質疑応答・まとめ |
| 5-1 DfAM成功のためのまとめ ①3Dプリンタは万能ではないが、従来工法では不可能な複雑形状を容易に製作できる ②DfAMを通じた「好循環」:目的・ゴールから適した方法を選定し、活用用途を広げる 5-2 質疑応答 |
| □解説2(15:30~17:00) |
| 「設計者のための「小さく始める」デジタルツイン活用術〜~手戻りゼロを目指す!CAE・BOM・動画連携による「試作レス」開発の第一歩~ (講師:神上コーポレーション株式会社 顧問・構造アナリスト 平池 学 氏) |
| 1.デジタルツインは「現場」から始まる |
| 1-1 なぜ今、デジタルツインなのか? ~サイバー空間(PC内)でモノづくりを完結させる意義~ 1-2 大規模システムは不要! 設計者の「手元」から始めるスモールスタートの考え方 1-3 成功事例に学ぶ:試作回数激減と期間短縮のインパクト |
| 2.【実践】3つのツール連携で実現する「試作レス」開発 |
|
2-1 【CAE連携】 設計しながら即検証! |
| 3.開発プロセス変革へのロードマップ |
| 3-1 フロントローディングの現実解 ~失敗はサイバー空間で出し尽くす~ 3-2 フィジカル(現実)とサイバー(仮想)の整合性をどう高めるか 3-3 3Dプリンタ活用による「最終確認」だけの試作へ 3-4 設計部門から全社へ広げるステップ ~まずは自分が変わる、そして周囲を巻き込む~ |
| 4. まとめ・質疑応答 |
| ①今日から始めるデジタルツインの第一歩 ②質疑応答 |
|
【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |