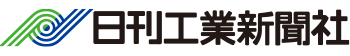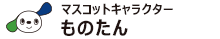セミナー
受注から設計、量産までの工程を通して理解を深める
品質知識とともに学ぶ
実践!プラスチック製品設計
開催主旨
普段何気なく使っている機器、たとえばスマートフォンを1つ取り上げても、キズ防止のカバーに始まり、サイドボタン、カメラ部、充電部のコネクタ、内部にはもっと多くのプラスチック部品が使用されています。それぞれの機能や耐久性を実現するために、適切な「材質選択」「形状設計」などにより「品質」を作り込むことが重要です。
周囲を見渡せば、プラスチックが使われていない製品はほとんどないといっても過言ではないくらい広範囲にプラスチックが使われています。それ故ものづくりにおいては、プラスチックを良く知ることはもちろんのことですが、これを製品という「形」へまとめ上げていく過程で『どのように品質を作り込めば良いのか』を知ることも同じくらい重要なことなのです。
本セミナーは、プラスチック製品設計者をはじめ、「製品化プロセス」の品質作り込みに携わる諸部門の方も想定しております。また、ものづくりの受注段階から量産までの流れを通して、どこに品質ポイントがあるのかを早期に知ることが必要な新入社員の方にも、自然に話の内容に入っていけるよう構成しています。
最初に「ものづくりの流れ」を説明いたします。次にプラスチックのものづくりには欠かせない3本柱「金型」「樹脂(プラスチック)」「成形加工」の基礎知識を解説いたします。続いて、パソコン作業やCAD設計で使用する「キーボード製品」を題材にして、「製品の受注から量産まで」の製品設計の実践について、事例を交えながら説明いたします。設計場面における設計手法や品質知識についても説明いたします。
当日は、題材のキーボード製品および分解ユニット/部品を元に設計の考え方を説明します。また技術トレンドといたしまして、2025.10月開催の国際プラスチック博覧会(K2025、ドイツ)の視察報告および同博覧会で入手の成形品サンプルを展示いたします。さらに成形不良現象の理解のため「成形不良サンプル」も展示いたします。実際に手に取って、見て触れることで、より理解が深まることとと思います。みなさまのご参加をお待ちしております。
習得可能知識
1)プラスチック製品設計の諸留意点
2)量産化までに活用する品質知識
3)射出成形金型の知識
4)樹脂材料の知識
5)成形加工の知識
6)コストの知識
7)最新の技術トレンド
8)現物で知る主要な成形不良
受講対象者
新入社員の方(ものづくりの仕方と品質知識を早い段階で学びたい)
設計デビューされる方(順を追って品質を作り込んでいくステップを学びたい)
プラスチック設計の経験がある方(3~4年)(自身の知識を整理したい)
品質手法をどのように設計プロセスで活かせば良いかを知りたい方
研究・開発部門、購買・資材部門、成形部門、品質保証/品質管理の方
セミナーにご参加いただいた方へ「新人製品設計者と学ぶ プラスチック金型の基礎」をテキストの副読本として贈呈いたします。
概要
| 日時 | 2026年 5月 21日(木)10:00~17:00 (9:30 受付開始 休憩12:30~13:30) |
|---|---|
| 会場 | 日刊工業新聞社 東京本社 セミナールーム ※会場には受講者用の駐車場が有りません。必ず最寄りの公共交通機関でご来場ください。 ※当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 |
| 受講料 | お一人様:48,400円(資料含む、消費税込) 受講にあたり |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 問い合わせ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 事業推進部(セミナー係) TEL: 03-5644-7222 FAX: 03-5644-7215 E-mail : j-seminar@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
講師
会場アクセス
-
日刊工業新聞社 東京本社
セミナールーム
中央区日本橋小網町14ー1
住生日本橋小網町ビル - セミナー会場案内図
プログラム
| 1.プラスチック製品のものづくり概要 |
| 製品受注、設計から量産までの各工程の留意点 |
| 2.プラスチックものづくりで重要な「3本柱」 |
| 1)「射出成形法」とは? 2)「金型」とは? ①金型の構造(2プレート/3プレート金型、モールドベース) ②金型の機能(「流す」「形を作る」「固める」「取り出す」「エアー排出」) 3)「樹脂」とは? ①熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂 ②結晶性と非結晶性、成形収縮率、特性改質、樹脂体系と種類 |
| 3.実践!プラスチック製品設計 |
| 1)「注文」を取る! ①技術検討と見積もり ②量産化難易度と品質保証体系 2)「要求事項」を明確にする! ①情報を整理して書類にまとめる ②QFD(品質機能展開)の活用 3)「製品設計」をする! ①QCDを満足するように具体化する ②サブ機能の設計具体例 4)「機能」を確かめる! ①フック形成と抜去力 ②FMEA(故障モードとその影響解析)の活用 5)「金型設計」をする! ①成形品生産仕様とは ②成形品仕様と金型設計 6)「試作」をする! ①金型製作仕様書 ②デザインレビューと性能試作のポイント 7)「性能」を確かめる! ①製品の信頼性試験 ②信頼性試験の判定 8)「金型判定」をする! ①量産試作用の成形品検証 ②公差緩和と特採表図面 9)「量産」を開始する! ①部品認定作業 ②工程認定と顧客オーディット |
| 4.技術トレンド、他 |
| 1)国際プラスチック博覧会(K2025 、ドイツ、デュッセルドルフ)視察報告 ①入手の成形品サンプル展示 ②動画視聴 2)主要な成形不良サンプル展示 |
| ※実際に手に取り、見て、触れて理解できます |