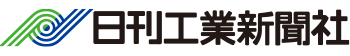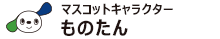セミナー
【ライブ配信セミナー】
「設計の見える化」が失敗する理由
設計ナレッジの可視化と標準化による設計高度化実践講座
~「脱」属人的設計!仕様/諸元の「見える化」標準化による設計効率化/設計自動化のアプローチ~
開催主旨
「設計ナレッジを可視化し、属人的な設計から脱却する」
「標準化をして効率的な設計をする」
「引退間近のベテランの頭の中を見える化する」
いわゆる「設計の見える化・設計ナレッジ(暗黙知)の形式知化」が10年以上前から掲げられていますが、多くの企業で活動が進んでいないというのが実態です。
活動が立ち上がっても、「忙しさ?」を理由に活動が中断してしまうケースが大半です。
なぜ、10年かかっても上手く進められないのか?
その理由の大半は、ナレッジ可視化・標準化・技術伝承の目的/推進方法/啓蒙活動に「根本的問題」があるからです。
「設計の見える化・設計ナレッジ(暗黙知)の形式知化」を進めるぞ!
となると、大半の設計部門が見える化をゴールとし、ひたすら「マニュアル作成」活動になりがちです。
結果、誰も見ない、読まない、読めない、使えないマニュアルが氾濫し、暗黙知が形式知にもならず、ベテランの引退とともにそのまま消えていく…というのが「設計改革の進まない10年」の真実です。
「頭の中を書き出すだけだから、ちゃんと時間をとって、思い出して書いてさえくれればいい。」そう簡単に考えているから失敗するのです。
自分の考えを整理し書き出すことはそう簡単ではありません。
「思考を言語化する」適切なアプローチを理解することで初めて、忙しい中でも「設計の見える化」を進めることができます。
また、本講座ではナレッジを「活用」し、標準化/自動化することで、効率化を実現させる手法を解説し、ナレッジの鮮度を保つための「改訂」の運用方法についても解説を行います。
本当に「設計を見える化」し、設計改革を進めるためのナレッジの「可視化」「活用」「改訂」を体系的に学んでください。
■受講対象者
・製造業
・経営者(CTO、CIO、CFO)
・開発部門・設計部門・設計管理部門の管理職から担当者
・情報システム部門の管理職から担当者
・経営改革・業務改革に携わっている管理職から担当者
■進呈書籍
お申込みいただいた方には、講師著『儲かるモノづくりのための PLMと原価企画<実践編>』(東洋経済新報社刊)を無料進呈します。
本セミナーのテキストは、PDFにてお送り致します。
※お申込みの際に、テキストを受け取れるメールアドレスを記入して下さい。
(申込アドレスと異なる場合は、申し込みフォームの備考欄にてお知らせ下さい。)
概要
| 日時 | 2026年 5月 22日(金)10:00~17:00 (9:30 ログイン開始)※昼休憩1時間あり |
|---|---|
| 会場 | WEBセミナー WEBセミナーは、WEBミーティングツール「Zoom」を使用して開催いたします。 ※当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 ブラウザとインターネット接続環境があれば、どこからでも参加可能です。 |
| 受講料 | お一人様:48,400円(資料含む、消費税込) 受講にあたり |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 申込締切日について | 2026年5月21日(木)17:00〆切 |
| 問合せ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 事業推進部(セミナー係) TEL: 03-5644-7222 FAX: 03-5644-7215 E-mail : j-seminar@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
講師
プログラム
【理論編】
| ① 標準化のよくある失敗 |
| 1. なぜ標準化は失敗するのか 2. 「標準」を作っても、「様々な顧客要求」に答えられない 3. 標準図を作っても使ってくれない 4. 設計マニュアルを作っても読まれない。改訂されない。 |
| ② ナレッジを組織の資産に変える |
| 1. 「属人的設計」は競争力を奪う 2. ナレッジ可視化はマニュアル作成ではない 3. ナレッジの見える化の4要素とは 4. 設計を知っていることと、言語化できることは別 |
| ③ 標準化を競争力につなげる |
| 1. 脱、流用設計。脱、属人設計。 2. 属人設計から脱却するための設計標準化の方向性 3. 図面の標準化と設計思想の標準化を使い分ける 4. 企画量産型と個別受注型における標準化の違い |
| ④ 少人数・短期期間での効果的な進め方 |
| 1. 標準化活動の最適なメンバー構成 2. 標準化活動の立ち上げ方(経営層への説明方法。効果説明) 3. 活動の進め方(大まかな活動ステップ) 4. 専任化できない中でナレッジ整備を進めるコツ |
【実践編】
| ⑤ 顧客要求を最大限に活かす仕様管理のポイント |
| 1. 要求仕様を見える化と一元管理するポイント 2. 要求仕様を傾向管理し、案件間での横串を通す管理の仕組み 3. 失注分析を可能にし、仕様提案や機種開発に活かす方法 |
| ⑥ 設計ルールを見える化し、標準化させる |
| 1. 設計を構造的に整理する ・要求仕様→設計仕様→方式→寸法の構造整理 ・要求仕様→レイアウトパターン→配置の構造整理 ・設計諸元→設計図書の構造整理 2. 設計ナレッジを設計ルール(標準)として整備する ・性能計算・性能チェックのルール ・基本形状・方式選定のルール ・相似形(寸法など)のルール 3. 標準を決める際のポイント ・標準化の3ステップとは ・バラバラな顧客要求に対して、標準をどう決めるか ・「標準を守らせる」運用は間違っている |
| ⑦ 標準や設計ルールを使った設計自動化 |
| 1. 論理構成(150%BOM)を用いた構成決定・部品選定の自動化 2. 設計諸元の自動選定 3. CADの自動モデリング・自動作図 4. 設計自動化とAI |
| ⑧ 標準やナレッジの改訂と若手人材育成 |
| 1. 標準の改訂は、検図の運用を見直し ・自己申告制の検図からの脱却 ・標準からの差異リストで標準改訂を促す 2. 標準の改訂は設計部門が実施すると失敗する 3. 若手にナレッジを共有・読ませる運用のコツ |
| 【ライブ配信セミナーに伴う注意事項について】⇒ 【詳細はこちら】 ※必ずお読みください(お申込みを頂いた時点でご同意頂いたとみなします) |