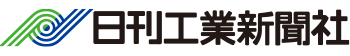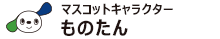| ①7/17(木)10:00-12:00「新たな時代の安全:協調安全(Collaborative safety)」 |
【チェア】
■吹田 和嗣 博士(工学):セーフティグローバル推進機構 理事、大同大学 教授
■Professor Dr Rolf Ellegast:Institute Director, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance(IFA)
【本セッションの概要】
製造現場では協働ロボットの普及が進み、機械と作業者が協業、協働して作業を行う場面が増加しています。しかし、人と機械が同じ空間や時間を共有して作業する現場では、従来のように物理的な手段で人と機械を隔離する安全対策が現実的でない場合が多く見受けられます。
このような状況を踏まえ、人と機械が協働・協調して作業を行うためには、ICTを活用した新しい安全概念である「協調安全(Collaborative Safety)」が求められます。「協調安全」とは、人、機械、環境が相互に連携することで、物理的な隔離に依存せず、安全かつ効率的に作業を進める仕組みを構築する考え方です。
本シンポジウムでは、ユーザー、機械メーカー、安全機器メーカーの視点から、「協調安全」の実現に向けた技術、実装事例、課題を紹介して、未来の製造現場における人と機械の新たな関係性を提案します。
【本セッションの構成】
■基調講演1「Safety & Security for Health and Well-being」
(Thomas Pilz:Managing Partner, Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern (Germany))
■基調講演2「協調安全を見据えたモノづくりの未来とドイツ―日本連携技術」
(横瀬 健心:デンソー FA事業推進部 部長)
(Werner Kraus:Head of Automation and Robotics Division, Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA)
■「モノづくり現場における機械安全の課題と協調安全による解決に向けたモノづくり委員会の活動」
(延廣 正毅:トヨタ自動車 安全健康推進部 ユニット支援室 技術プロジェクトグループ 主幹、IGASPモノづくり委員会 委員長)
■「初めてでも簡単に使える安心・安全の協働ロボットによる製造現場の自動化」
(森岡 昌宏:ファナック ロボット研究開発統括本部 ロボット機構研究開発本部 技師長)
■「サインを活用した協調安全方策の動向と標準化に向けた展望」
(水口 大知:アトリエ 代表取締役社長)
■「i3-Mechatronics によるデータを軸とした次世代モノづくり」
(西邑 孝史:安川電機 ロボット事業部ロボット技術部マニピュレータ・アプリケーション技術部 自律技術開発課 担当課長)
■「パナソニック オートモーティブシステムズ(PAS)における協調安全・健康取り組みのご紹介」
(菊池 栄成:パナソニック オートモーティブシステムズ JPオペレーション本部 生産戦略・技術センター 生産技術戦略部 工法革新課 課長)
|
| ②7/17(木)14:00-16:00「人間計測・人間拡張でウェルビーイング経営を支援する」 |
|
【チェア】
■持丸 正明:産業技術総合研究所 フェロー
【本セッションの概要】
オフィスやサービス現場で働く従業員の行動や生理状態を計測する人間計測技術、さらには、そこから業務の状態、身体や心理的な状況を計算して可視化提示することで従業員の心身の状態を高め、さらにはリモートロボット技術で遠隔就労を実現するという人間拡張技術が研究開発されている。さまざまなウェアラブルセンサデバイスが利用可能になっていることや、生産性向上に向けて従業員のQuality of Working (QoW) を向上させようとする企業側の意識変化によって、これらの技術が職場やサービス現場に適用され、ウェルビーイング向上に役立ち始めている。
一方で、企業経営においても従業員の心身の健康を考える健康経営、さらには、ウェルビーイングを実現するためのウェルビーイングマネジメントが重要視され始めている。2024年には、ISO TC314においてウェルビーイングマネジメントのガイドライン標準が策定された。このような標準に沿って実現されたウェルビーイングマネジメントは、統合報告書などに記載されて投資家を含むさまざまなステークホルダーの目につくことになる。これが、企業経営におけるウェルビーイングマネジメント推進の原動力になると期待されている。
本セッションでは、就労現場のウェルビーイングに資する人間計測、人間拡張技術の研究開発と適用事例を紹介するとともに、ISO TC314におけるウェルビーイングマネジメントのガイドライン標準の策定と、それを活用する日本企業における健康・ウェルビーイングマネージメントの動向について紹介する。
【本セッションの構成】
■基調講演「Digitalizing occupational safety: exposure documentation with OMEGAone」
(Manuel Kühn:Section Manager "Development and Organization in the MGU", Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (IFA))
■「産業現場の従業員計測に基づくQoW評価に関する研究」
(一刈 良介:産業技術総合研究所 人間社会拡張研究部門 研究グループ)
■「人とロボットの協奏:ウェルビーイングな未来を拓く」
(田中 宏和:リモートロボティクス株式会社 代表取締役社長)
■「ウェルビーイングの促進を支援する国際規格の開発:ISO 25554の紹介と今後の展望」
(細野 美奈子:産業技術総合研究所 ウェルビーイング実装研究センター ヒューマンステートデザイン研究チーム 主任研究員)
■「日本企業における健康・ウェルビーイングマネージメントの動向」
(浅野 健一郎:社会的健康戦略研究所 代表)
■「Nittoグループが目指す自発的なチャレンジを促す風土作りとは」
(坂東 保治:日東電工株式会社 日本エリア・人財ガバナンス本部長兼 コーポレート人財本部 副本部長)
■「責任あるAIを実現するAI安全品質マネジメントの社会実装に向けて」
(難波 孝彰:パナソニックホールディングス株式会社 シニアリードエンジニア)
|
| ③7/17(木)16:00-18:00「人間中心のウェルビーイング・テック~行動分析からデジタルヒューマンまで~」 |
|
【チェア】
■多田 充徳:産業技術総合研究所 デジタルヒューマン研究チーム長
【本セッションの概要】
生産現場では、効率性や生産性の向上が重視される一方で、労働者の健康や負担軽減といった労働環境におけるウェルビーングの向上も重要な課題となっている。そこで、人間の行動特性や身体特性に応じて労働環境をデザインするための技術に注目が集まっており、ここではそれを人間中心のウェルビーイング・テックと呼ぶ。
現状でもスマートウォッチやセンサを内蔵した作業着を用い、労働者の心拍数や体温をリアルタイムにモニタリングすることで、過労や熱中症を予防するシステムが運用されている。これは、異常検知に基づき労働者の安全性向上を実現するウェルビーイング・テックの1つである。
人間中心のウェルビーイング・テックとは、この考えを一歩進め、人間の特性を明示的にモデル化し、これを用いて認知・身体負荷の軽減を目指すものである。例えば、労働者の行動特性や身体特性がモデル化できれば、それを用いた行動シミュレーションに基づき、より良い現場環境がデザインできる。また、労働者のモデルに加えて、現場における労働者の現況がモニタリングできれば、アシストスーツや協働ロボットを用いた即時的な作業支援が実現できる。
本セッションでは、より良い現場環境のデザインと即時的な作業支援という2つの観点から、人間中心のウェルビーイング・テックの現場での活用事例や,最新の研究事例を紹介する。行動分析、工程シミュレーション、アシストスーツ、そしてデジタルヒューマンのように多岐に渡る4つの講演を通じて、それぞれの技術について理解を深めるとともに、相互連携の可能性を議論する機会としたい。また、本セッションが人間中心のウェルビーイング・テックが現場で活用される契機となることを期待したい。
【本セッションの構成】
■基調講演「Ergonomic Risk Assessment with Inertial Measurement Units and CUELA」
(Christoph Schiefer:Section Manager "Innovation work design", Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (IFA))
■「行動分析学による職場最適化のためのウェルビーイングの見える化・定量化」
(北條 理恵子:長岡技術科学大学 准教授)
■「アシストスーツによる持続可能な労働環境の実現:軽労化という考え方」
(田中 孝之:北海道大学 大学院情報科学研究院 教授)
■「デジタルヒューマン技術を用いた人ロボット協調」
(丸山 翼:産業技術総合研究所 人工知能研究センター デジタルヒューマン研究チーム)
■「デジタル活用による製造業のウェルビーイング向上」
(志子田 繁一:川崎重工業 技術開発本部 システム技術開発センター システム基盤技術開発部 特別主席研究員)
■「建設機械の開発におけるデジタルヒューマン技術の活用」
(古谷 健:小松製作所 開発本部 キャブ開発センタ エキスパートエンジニア)
■「工程シミュレーションGEN-VIRの研究開発と施工現場での活用」
(伊東 裕司:トヨタ自動車 未来創生センター R-フロンティア部 生産革新研究領域 リサーチリーダー)
|
| ④7/18(金)10:00-12:00「ウェルビーイングに向けた人機械協調技術」 |
|
【チェア】
■谷川 民生:産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター 研究センター長
■Professor Dr Rolf Ellegast:Institute Director, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance(IFA)
【本セッションの概要】
AIやロボット技術の発展により、人と機械との協業の場が多くなってくることが予測される。特に、今後のAIの活用には、技術的だけでなく倫理的にも議論する必要がある。
本セッションでは、人のWell-beingを実現するために、どのようにAIを含む機械を活用すべきか、そのための技術課題として何をすべきかについて議論する。
【本セッションの構成】
■基調講演①「Making workplaces safer by using AI: assistance system on a sliding table saw」
(Thomas Bömer:Deputy Head of Department “Accident Prevention: Digitalisation –Technologies“, Section Manager “Industrial Security – Functional Safety”, IFA)
■基調講演②「Robotics Policy ~Realization of well-being through the development of robots~」
(石曽根 智昭:経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 室長)
■「Smart prevention: real-world data and AI solutions for (near) fall detection」
(Moritz Schneider:Team Leader "Data Science and Artificial Intelligence", IFA)
■「みんなが安心して暮らせる高齢化社会をサポートするために ~hinotoriサージカルロボットシステム~」
(吉田 智一:シスメックス 取締役 常務執行役員CTO)
■「川崎重工業における人協調ロボットの取り組み」
(加賀谷 博昭:川崎重工業 社長直轄プロジェクト本部 執行役員、本部長)
|
| ⑤7/18(金)14:00-16:00「協調安全を実現するためのモノづくり企業における包括的アプローチの実践事例」 |
|
【チェア】
■梶屋 俊幸:セーフティグローバル推進機構 理事
■Professor Dr Rolf Ellegast:Institute Director, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance(IFA)
【本セッションの概要】
従業員の安全・健康・ウェルビーイングは労働人口の減少や働き方改革が進展するモノづくり企業において、ますますその重要性が高まっている。
この実現に貢献できるツールのひとつが、人、機械、環境がリスク情報連携して人に安心を与える協調安全であり、これを効果的かつ持続的に現場で実践するには、技術的側面の他に、要員の適性、組織やマネジメント、ルール形成といった包括的なアプローチが不可欠である。
本セッションでは、自動車や電機セクターを中心としたモノづくり企業における独自の取組みを紹介し、聴講者の所属企業に対し何らかのヒントを与えることを狙いとする。
【本セッションの構成】
■基調講演「Building and managing psychosocially resilient safe workplace - Context. Culture. Constraints」
(Stuart Hughes:Immediate Past President of the Institution of Occupational Safety and Health (IOSH))
■「New ways to communicate about security issues worldwide」
(Jonas Stein:Scientist, IFA)
■「Why Market Surveillance is key for Citizens, Industry and Governments ?」
(Pierre Selva:VP Conformity Assessment & Market Surveillance, Strategy & Sustainability,Schneider Electric)
■「Defeating of safeguards on machinery: a holistic approach for prevention」
(Stefan Otto:Research Officer,IFA)
■「Designing safe, smart and efficient factories utilizing emerging technologies」
(Timothy T. Duffy:Senior Manager, Conformity Assessment Global Product Standards & Regulations, Rockwell Automation)
■「Safety 2.0適合審査登録制度と要員力量認証システム」
(有山 正彦:セーフティ アセッサ、日本認証株式会社 事業企画部 部長)
■「AIマネジメントシステム適合性評価制度の確立に向けて」
(山内 徹:日本情報経済社会推進協会 常務理事)
|
| ⑥7/18(金)16:00-18:00「人口減少に備える社会における人機械協調」 |
|
【チェア】
■中坊 嘉宏:産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター ディペンダブルシステム研究チーム長
【本セッションの概要】
今後、長く続くと予想される日本の労働人口の減少、および人口の超高齢化は、生産のみならずサービスも含めた社会の全般にわたって大きな影響を及ぼすことになる。
そのような状況においても、快適で安全な社会を維持していくためには、人間を中心に考え、すべての人のウェルビーイングを前提として可能な限りの自動化を推し進め、人と機械とが協調する新たな社会システムを構築することが必要であると考えられる。
本セッションでは、そうしたビジョンを前提にサービスロボットやウェルビーイング・テックの社会への導入について、安全性や効率性、実現性などについて、現状の技術と今後の展開を見据えた議論を行う。
【本セッションの構成】
■基調講演「NVIDIA Halos - AI Safety from Autonomous Vehicles to Broader Physical AI」
(Riccardo Mariani:VP Industry Safety, NVIDIA)
■「Clinical AI and Trust: Bridging Algorithmic Transparency and Human Factors」
( Nicolas Frey:Research Associate, Working Group Data Analytics, Institute of Medical Informatics, Charité, Berlin, Germany)
■「ヘルスケアジャーニーを実現するためのシスメックスのアプローチ」
(辻本 研二:シスメックス 執行役員 次世代医療事業開発室長)
■「表情解析技術を用いたBHQ推定アルゴリズムの開発と地域住民の脳健康状態認知促進に向けた取り組み」
(難波 嘉彦:パナソニックホールディングス プロダクト解析センター 新規事業開発室 室長)
■「コモングラウンドという概念:現実空間と情報空間が交差する場」
(豊田 啓介:東京大学生産技術研究所 人間・社会系部門 豊田研究室 特任教授)
■「コモングラウンドの国際標準化に関する現状と今後の可能性」
(長嶋 孝之:PwCコンサルティング Technology & Digital Consulting Technology Laboratory パートナー)
■「人共存に向けたサービスロボットの安全確保の取組み」
(岡本 球夫:株式会社SHIN-JIGEN エッジAI事業部 ヴァイスプレジデント)
■「ソーシャルロボットの安全性確保の取り組み」
(蓮沼 仁志:川崎重工業 社長直轄プロジェクト本部 ソーシャルロボット事業戦略部 基幹職)
|