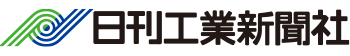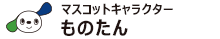セミナー
技術者・設計者 必修!
事例でわかる
ゴム・プラスチックの材料トラブル対策
材料別・原因別で対策のポイントを徹底理解!
開催主旨
ゴム・プラスチックなど高分子材料の最大の欠点は、無機材料に比べて劣化しやすいこと。使用初期には何ら問題がなくとも、時間の経過とともに物性値が低下し材料としての機能・性能が損なわれてきます。なかには、脆性化した材料が破損・欠落し異物として装置・システムに深刻なダメージを与え、重大事故に発展するケースもあります。材料の性能・機能を維持し、製品の安全性を確保するためには、適切な材料選択と様々なケースを想定した劣化防止策が不可欠です。対策には、個々の材料物性に関する知識はもちろんのこと、実際に起こったトラブルからその要因を抽出、製品設計や運用のノウハウとして蓄積・活用することが有効です。材料が使用される環境からの影響も大きく、個別の事案毎にトラブルに至るストーリーが異なります。最近では地球環境の温暖化によって、これまでには想像がつかないようなきっかけでトラブルに発展するケースが増えています。
本セミナーでは,主要なゴム・プラスチック材料の欠点や使用上の留意点を学ぶとともに、実際のトラブル事例から破壊に至るメカニズムを紹介し、その対策を学びます。長年にわたる材料トラブルの解析経験をもとに原因別・材料別の設計ポイントや盲点を指摘していきます。化学反応を主因とする材料劣化の兆候は、ミクロンオーダーでしか捉えられないことが多く、いわば「見えない敵」と言えます。本セミナーでは、理論と経験をフル活用して解決の糸口を見出す術を身につけます。なお、セミナー後には、個別の質問・相談にも対応致します(時間制限有。質問時は会社名、お名前がなくとも結構です)。
受講対象者
樹脂材料にかかわる技術者・研究者全般:
1.プラスチック製品、ゴム製品、機械設計者・技術者
2.製品トラブルの原因を究明する品質管理・品質保証担当者
3.製品を開発・改良したいと考える研究開発担当者
進呈書籍
「ゴム・プラスチック材料の原因別トラブル事例と対策」(大武義人著、日刊工業新聞社刊。330頁)を無料進呈致します。
概要
| 日時 | 2025年 12月 4日(木)10:00~17:00 (9:30 受付開始 休憩12:30~13:30) |
|---|---|
| 会場 | 日刊工業新聞社 東京本社 セミナールーム ※会場には受講者用の駐車場が有りません。必ず最寄りの公共交通機関でご来場ください。 ※当日の録音・録画は固くおことわり申し上げます。 |
| 受講料 | お一人様:48,400円(資料含む、消費税込) 受講にあたり |
| 主催 | 日刊工業新聞社 |
| 問い合わせ先 | 日刊工業新聞社 総合事業本部 事業推進部(セミナー係) TEL: 03-5644-7222 FAX: 03-5644-7215 E-mail : j-seminar@media.nikkan.co.jp TEL受付時間:平日(土・日・祝日除く) 9:30-17:30 |
| FAX申込みについて |
講師
会場アクセス
-
日刊工業新聞社 東京本社
セミナールーム
中央区日本橋小網町14ー1
住生日本橋小網町ビル - セミナー会場案内図
プログラム
| 1. ゴム・プラスチック材料にまつわるトラブル防止の鉄則 |
| ・使用する材料や、製品を使う環境をよく知ったうえで材料選択する ・実際のトラブルに学んで、設計に生かす ・まれに起こる、原因のわかりづらいトラブル事例とその対処法 ・ゴム・プラスチックの破損・破壊の概要とトラブル調査の留意点(異物検出など) |
| 2.樹脂材料の特徴と欠点を知る |
| ・分子量および分子構造と高分子材料の物性 (1) 汎用プラスチック各種の特徴と欠点(PS、PE、PP,PVC、PMMA、ABS) (2) エンジニアリングプラスチックの特徴と欠点(PA(ナイロン)、POM、PBT、PET、PC、TPX) (3) 加硫ゴムと熱可塑性エラストマーの特徴と欠点(天然ゴム、イソプレン、ニトリル系、フッ素系、エチレン‐プロピレン系、クロロプレン系、シリコンゴム、スチレン‐ブタジエン系、ウレタン系、エポキシ、不飽和ポリエステル) |
| 3. [事例] 製品の破壊メカニズムとその対策 |
| ・様々な破壊のメカニズム(脆性破壊、延性破壊、疲労破壊ほか) [疲労劣化破壊] プラスチック:疲労劣化のメカニズム、PCとPVCの疲労例、PMMA製床板の破損例 ゴム:加硫ゴムの疲労に対する考え方、疲労劣化の検出法、分子構造の違いによる違い、疲労劣化防止法 [残留ひずみによるクラック]残留ひずみ発生のメカニズム、フィルムの残留ひずみとクラックの発生 [ソルベントクラック]ソルベントクラックのメカニズムと発生個所、環境応力き裂(ESP)と実例、ESP対策 [応力腐食割れ]応力腐食割れのメカニズムと原因となる樹脂と金属の接触、クロロプレンによるステンレス配管の応力腐食割れ |
| 4. [事例] 材料劣化のメカニズムとその対策 |
| [水による劣化]ゴム・プラスチックの水吸着性と劣化のメカニズム、水劣化時の酸化防止剤の流出とその対策 ① フッ素ゴムの温水劣化、②不飽和ポリエステルの変色、③ゴムパッキンの劣化による純水の汚染 [光による劣化]光と熱と水の相乗効果による劣化メカニズム、①紫外線吸収剤不足時の不飽和ポリエステルフィルムの劣化 [微生物による劣化]①微生物によるコンクリートの劣化、なぜ激増しているか、硫酸発生のメカニズム、エポキシコーティングの耐久性問題、コンクリートの強化と曝気対策、②学習する微生物による天然ゴム+スチレンブタジエンゴム製の劣化、経緯と劣化メカニズム、原材料のブレンド比率の変更による対策、③学習する微生物によるポリウレタンの劣化、ウレタン製の靴底・パッキン・スリーブの破損、④ゴム・プラスチックに添加した抗菌剤、防カビ剤が原因となったトラブル [オゾンによる劣化] オゾンによるブタジエン系ゴムの劣化、オゾンの作用とクラック発生機構、オゾン劣化と疲労劣化の判別、ゴムの種別による耐オゾン性の違い、①FF式ファンヒータ事故、経緯とアクリルニトリルブタジエンホースのクラック発生メカニズム、②様々な環境下でのオゾン劣化、火力発電所、船舶、 [油の浸透による劣化] ① アクリロニトリルブタジエンゴム製パイプ壁面からの油透過漏れによる発火、②廃油や再生油によるトラブル [金属との接触による劣化] 金属害(銅害)の対象金属と劣化メカニズム、①銅害によるポリウレタンチューブの変色、銅害が接着剤の接着力に及ぼす影響、銅害防止策 [リサイクルによる劣化] バージン品とリサイクル品に含まれている添加物の違い、①様々なリサイクル品に多量に含まれる酸化防止剤によるトラブル、②すでに劣化したLED製品の再生例 |
| 5.質疑応答・トラブル相談 |